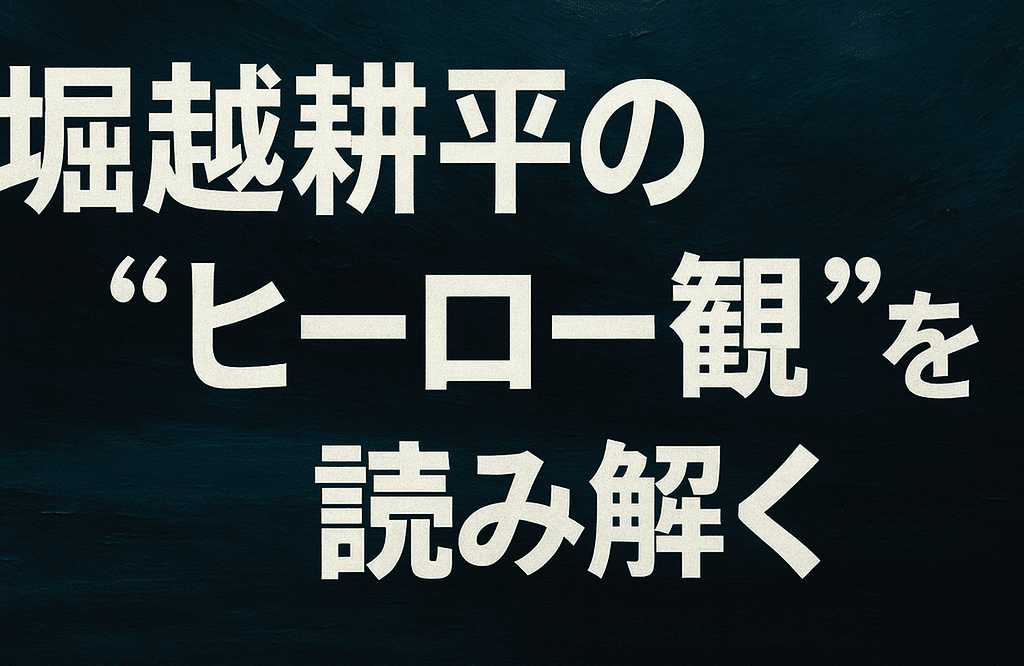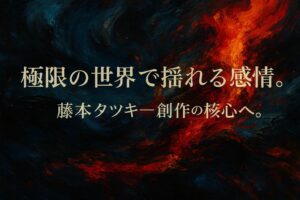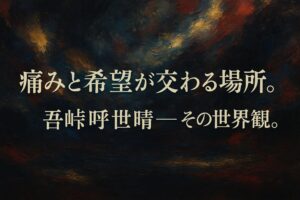『僕のヒーローアカデミア』に一貫して流れているのは、堀越耕平が長い時間をかけて育ててきた“ヒーローとは何か”という問いだ。強さの象徴として描かれる存在だけでなく、迷いながらも誰かを守ろうとする姿にこそヒーローの本質が宿るという視点が、彼の作品にははっきりと刻まれている。幼少期の原体験、読切時代の模索、連載のなかで得た挫折や学び。それらが折り重なることで、独特のヒーロー像が形作られていった。本記事では、作品や発言を手がかりに、その思想がどのように育ち、どのような形で描かれてきたのかを丁寧にたどっていく。
子ども時代に芽生えた“ヒーローへの憧れ”
堀越耕平のヒーロー観は、幼い頃から自然と育まれてきたものだ。幼稚園の頃には、思い浮かんだイメージをそのまま絵にして楽しんでおり、「描くこと」がすでに日常の一部になっていたという。小学生の時に『ロックマンX2』のキャラクターを描いたところ、友人から「その絵がほしい」と言われた経験は、絵を描く喜びを強く意識するきっかけとなった。この体験が“漫画を描く側”への最初の橋渡しになったことは、本人もたびたび語っている。
夢中で読み続けた作品として、彼は『ドラゴンボール』を繰り返し挙げている。とりわけセルゲーム編の迫力に惹かれ続け、「最強の存在は、見ただけでわかるような力強さを持っていてほしい」という感覚を抱いたという。この思いは、後にオールマイトの体格や佇まいにそのまま息づくことになる。また、中学生の頃に観たサム・ライミ版『スパイダーマン』は、構図や影の付け方、画面の勢いに魅了され、アメコミの表現を研究するきっかけになった。彼の作画に見られる大胆なシルエットや光の扱いは、この時期の影響を色濃く反映している。
好きなヒーローとして挙げる名前は、悟空、スパイダーマン、そしてアンパンマン。いずれも“現れた瞬間に場の空気を変え、人を安心させる存在”だという。力そのものではなく、登場したときの安心感や背中の大きさにこそヒーローの本質がある――そんな価値観は、子ども時代に抱いた素朴な憧れからすでに始まっていた。『僕のヒーローアカデミア』でオールマイトが象徴的な登場を見せる場面は、この幼少期の原体験が、そのまま現在の創作に結びついた証と言えるだろう。
読切「僕のヒーロー」に刻まれていた“行動する意志”という原型
堀越耕平のヒーロー観が、最も早い段階で明確な形をとって現れたのが読切作品「僕のヒーロー」だ。大学在学中に「ヌケガラ」で手塚賞佳作を受賞したあと、「テンコ」「僕のヒーロー」「進化ラプソディ」などを赤マルジャンプに発表していく過程で、彼は“特別な力を持たない主人公”を軸にした物語をすでに描き始めていた。のちに『逢魔ヶ刻動物園』へとつながるこの時期の作品群には、後年の創作哲学が自然とにじんでいる。
「僕のヒーロー」の主人公・緑谷弱は、ヒーロー用品を扱う会社の平凡なサラリーマンだ。虚弱体質で、自分自身もヒーロー向きではないと分かっていながら、“誰かを助けたい”という思いだけで夜の街に立つ。圧倒的な能力や華やかな必殺技を持つキャラクターではなく、夢と憧れだけを頼りに動く普通の人間が物語の中心に置かれている点が、この作品の特徴だ。弱さを抱えながらも、行動したい気持ちだけは揺るがないという姿は、作者が当初から大切にしていたテーマをそのまま映し出している。
さらに、この読切には連載版『僕のヒーローアカデミア』につながる重要な要素が数多く存在する。ヒーローが制度化された社会、理想と現実の間で葛藤する主人公、そして“戦う力がない人間でもヒーローたり得るのか”という問い。これらは連載版の核になったテーマであり、読切時点ですでに明確な形を持っていた。『逢魔ヶ刻動物園』5巻の収録時にも“プロトタイプ”として位置づけられたように、この短編は後の大作の根をつくった一作といえる。
『戦星のバルジ』終了後、次のテーマが見つからず悩んだ時期に、堀越が「自分が一番楽しく描けたのは『僕のヒーロー』だった」と振り返ったというエピソードは象徴的だ。つまり、読切時代から温めていた“力よりも意志を信じる主人公像”こそが、彼にとって揺るぎない軸であり、後の『ヒロアカ』に受け継がれたヒーロー観の原型だったのである。
二度の打ち切りが気づかせた“そばにいる人こそヒーロー”という視点
初連載『逢魔ヶ刻動物園』は2010年から2011年にかけて連載され、全5巻で完結した。続く2作目『戦星のバルジ』も短い期間で幕を閉じ、堀越耕平は2作連続の打ち切りという厳しい現実に向き合うことになった。期待していた作品が思うように届けられなかった経験は大きな重荷となり、本人も「もう漫画を描けない」と感じるほど創作への意欲を失ったと語っている。新しいアイデアが浮かばず、漫画家としての自信が揺らいだ時期だった。
それでも再びペンを取れたのは、編集者や近しい人たちの支えがあったからだ。担当が変わったタイミングで何度も話を重ね、迷いを抱えたままでも前に進めるよう背中を押してくれた存在がいた。堀越は後年のインタビューで、「自分が苦しいときに寄り添ってくれた人をヒーローだと思った」と語っており、ヒーロー像が“憧れの象徴”から“身近で支えてくれる誰か”へと少しずつ変化していったことが分かる。
この価値観の転換は、『僕のヒーローアカデミア』の物語にも鮮明に反映されている。圧倒的な象徴として立つオールマイトだけでなく、デクの歩みを支えるクラスメイトや教師たちの存在が、物語の核として描かれているのは象徴的だ。華やかな能力の強さではなく、迷う誰かの背中にそっと手を添える行為そのものに“ヒーローの本質”を見いだす視点は、挫折の中で体験した現実から生まれたものだったと言える。
堀越耕平が語る“ヒーロー”は、完璧でも圧倒的でもない。それよりも、迷ったときに寄り添い、前へ進む力をくれた存在の姿を重ね合わせたものだ。この気づきが、ヒロアカに広がる多様なヒーロー像を支える芯となり、読者が作品を通して“自分の身近な誰か”を思い浮かべる理由にもなっている。
『ヒロアカ』で形になった“多層的なヒーロー観”──物語全体とキャラクターが示した答え
『僕のヒーローアカデミア』では、堀越耕平が抱いてきた“ヒーローとは何か”という問いが、物語全体の構造とキャラクターの生き方の両面から描かれている。作品の核にあるのは、「力の大きさではなく、どう行動するかでヒーローは決まる」という価値観だ。
その象徴が、ワン・フォー・オールの継承である。特別な力を持たなかったデクが、誰かを救いたいという意志だけで選ばれたという設定は、“行動する心”を重視する堀越の思想を最も端的に示している。OFAは単なる強化能力ではなく、過去の意志を受け取って次につなぐ“心の継承”として描かれる点も特徴的だ。
一方で、このヒーロー観はキャラクターごとに異なる形で表れていく。雄英という同じ環境にいながら、彼らの過去や価値観が違うため、たどり着くヒーロー像は決して一つではない。
デクは「反射的に手を伸ばす存在」をヒーローとして捉え、弱さを抱えながらも行動することで前へ進む。爆豪は幼少期から培ってきた“勝つことこそ正義”という信念に縛られつつ、他者の努力や痛みに触れることで価値観を少しずつ塗り替えていく。轟は家庭環境の影響から“どう生きるか”そのものを問われ、自分の意思で道を選び取ることを通じてヒーロー像を見つけていく。強さ、行動、自己決定──三者三様の答えが物語に厚みを与えている。
そして作品全体を牽引するオールマイトは、“見た者を安心させる存在”でありながら、肉体は限界を迎えつつある。弱さと覚悟が同居したその背中は、堀越が描きたかった「完全無欠ではなくても、人は誰かの光になれる」というメッセージを象徴している。
このように『ヒロアカ』では、ひとつの正解に収束するヒーロー像ではなく、キャラクターの数だけ異なるヒーロー観が存在する。物語の中で交わり、影響し合い、変化していくそれぞれの価値観が、作品全体の骨格となり、読者が“自分にとってのヒーロー”を思い浮かべられる余白を生み出しているのである。
作者自身の言葉に映る“ヒーローとは誰か”という視点の変化
堀越耕平のヒーロー観は、作品世界だけでなく、これまでの発言にも一貫して表れている。彼の言葉をたどると、幼い頃の憧れから、挫折を経験した後に生まれた実感まで、価値観がどのように育ち、どの方向へ広がっていったのかが見えてくる。
子ども時代に強い影響を受けた作品として、堀越は『ドラゴンボール』とサム・ライミ版『スパイダーマン』を挙げている。特に悟空の“強さの象徴”のような体つきには深い憧れがあり、そのイメージがオールマイトの造形に反映されたと語っている。アメコミに惹かれたきっかけも映画体験にあり、構図や影の付け方を研究しながら作画に取り入れたという。こうした発言からは、彼がヒーローに“強くあってほしい”という願いを抱いていたことがよく伝わってくる。
しかし、ヒーロー像は強さだけで形づくられるものではないと堀越は考える。その象徴がアンパンマンだ。周囲を安心させ、当たり前のように人を助ける存在への憧れは、彼の中でひとつの理想像となっていたとされ、ファンブックや関係者のコメントでも言及されている。強さと優しさ、その両方がヒーローに必要だという感覚は、この頃すでに根づいていた。
やがて、二度の打ち切りを経験した時期に、堀越のヒーロー観はさらに変化していく。新しい作品案を考えられないほど落ち込んだと語られるなかで、支えになったのは担当編集や周囲のスタッフだった。彼らが根気強く話を聞き、次のステップを一緒に模索してくれた経験は、「自分を助けてくれる身近な人もヒーローになり得る」という実感へとつながった。作中で“支え合う関係性”が重視されるようになるのは、この現実の体験が大きい。
そして連載が終わりに近づく頃、堀越が語るヒーロー像はより日常に寄り添ったものへと定まっていく。最終巻のプロモーションとして掲げられた「世界を救わなくても、人に優しい言葉をかけられるだけでヒーローになれる」という趣旨のメッセージは、作品世界だけでなく、現実の読者に向けられた言葉として広く反響を呼んだ。
これらの発言を踏まえると、堀越耕平のヒーロー観は“強さへの憧れ”から始まり、“身近な誰かを救う行為”へと深化し、最終的には“日常の中の小さな勇気”にまで拡張していったことがわかる。ヒーローは遠くの象徴ではなく、迷いながらも人のために手を伸ばせる存在――この考え方こそが、彼が10年間の連載を通してたどり着いた答えと言えるだろう。
連載終盤で浮かび上がった“ひとりでは成り立たないヒーロー像”
物語がクライマックスに向かうにつれ、『僕のヒーローアカデミア』におけるヒーロー像は、初期の“強さの象徴”からより複雑で人間的な姿へと変化していく。その変化を端的に示すのが、パラノーマル・リベレーション・ウォー後の、いわゆる“ダークヒーロー編”にあたるデクの単独行動のパートである。
デクは、オール・フォー・ワンや死柄木弔に狙われる立場になったことで、雄英の仲間を危険に巻き込みたくないという思いから自ら学校を離れる。プロヒーローと共に各地を巡り、ワン・フォー・オールの力を極限まで使い続ける日々を送りながら、次第に自分だけで戦おうとする姿勢が強まっていった。力を得たがゆえに孤立へ傾き、表情も言動も追い詰められた状態へと変わっていく。
しかし、その道を止めたのもまた仲間たちだった。クラスメイトはデクの行動をただ肯定するのではなく、“彼が救われる側でもいい”という前提のもとに向き合い、説得し、最終的に雄英へ連れ戻す。このやり取りは、ヒーローを“助ける側”だけに固定せず、“支えられるべき存在”としても描くという、終盤特有の視点を鮮やかに示している。
最終決戦では、デクの戦いと平行して轟、爆豪、飯田、麗日お茶子らがそれぞれの場所で“自分にできる助け方”を模索し続ける。オールマイトもまた、全盛期の力を失った身体のまま敵に立ち向かい、象徴としての完全無欠さではなく、“弱さを抱えながらも誰かを信じて踏み出す姿”を体現していく。力そのものではなく、心の在り方と関係性がヒーロー像の中心に据えられているのが分かる。
こうして物語の終盤に表れたヒーロー像は、ひとりの強者が道を切り開くものではなく、互いに支え合うことで立ち続ける“関係の中のヒーロー”という姿だった。孤独な自己犠牲ではなく、“助ける”と“助けられる”の往復の中にヒーロー性を見いだす視点は、連載後期に明確になったものだ。堀越耕平が10年の物語を通じてたどり着いたのは、力の大きさでは測れない、人と人とのつながりから生まれるヒーロー像だったのである。
物語が最後に示した“日常に生まれるヒーロー”という答え
クライマックスに向かう『僕のヒーローアカデミア』では、物語の視点が次第に“特別な力のある者”から“普通の人々”へと広がっていく。終盤で描かれるのは、大きな戦いの中心にいない人々が、恐れや迷いを抱えながらも誰かのために動こうとする姿だ。
象徴的なのが、いわゆる“黒デク編”だ。オール・フォー・ワンに狙われたデクは、仲間を巻き込まないために雄英を離れ、限界を超えて街を駆け続けるようになる。泥まみれで疲れ切った姿のまま雄英に戻ろうとしたとき、避難民の一部は不安や恐怖から彼を拒もうとする。自分たちの安全が脅かされるかもしれない状況で、すぐに手を差し伸べられない市民の反応は、現実感を伴った“普通の人々”の姿として描かれた。
そんな空気を変えたのが、麗日お茶子だった。彼女はデクをかばいながら、「ヒーローもまた傷つき、支えを必要とする存在であること」を市民に語りかける。すべてを理解してもらうことは簡単ではないが、それでも言葉を尽くし、市民たちも少しずつ不安と向き合いながら歩み寄っていく姿が描かれた。ここには、戦いに参加できない人々が“できる範囲で誰かを支える”という、静かなヒーロー性が表れている。
同じ終盤では、爆豪がデクに対して自分の過ちを認め、正面から謝罪する場面や、轟家がそれぞれの立場から問題に向き合い直すエピソードが描かれる。派手な戦闘ではなく、“言葉”や“選択”によって誰かの痛みに寄り添おうとする行為が、ヒーローの成長として位置づけられているのが印象的だ。
さらに、オールマイトの描かれ方も大きく変わっていく。かつて平和の象徴だった彼は、力を失った後も、人を励まし、信じ、最後には自分の限界を承知のうえで敵に立ち向かおうとする。全盛期のように圧倒的な勝利を収められなくても、弱い立場のまま誰かを思って行動する姿は、別の形のヒーローとして作品に刻まれている。
こうした終盤の描写を並べると、作品が最後に提示したヒーロー像がくっきりと浮かぶ。
それは――
「特別な力がなくても、恐れや迷いを抱えながらも、自分のできる一歩を誰かのために踏み出すこと」
という、きわめて日常的なヒーローの姿だ。
堀越耕平が10年にわたる連載で導き出したのは、世界を救う大きな奇跡だけがヒーローではないという視点だった。静かな勇気、寄り添う気持ち、誰かを信じようとする意志――作品のラストに残されたのは、派手なバトルを超えて、読者の生活とも地続きの“日常に宿るヒーロー性”だったのである。