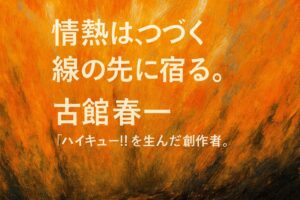『呪術廻戦』は、負の感情が形となって現れる世界を舞台にしながら、登場人物の迷いや弱さ、選択の重さを丁寧に描いてきた作品です。その背景には、作者・芥見下々が長年の創作の中で向き合ってきたテーマや、影響を受けた作品群、キャラクターを組み立てるための独自の手法があります。本記事では、これまでのインタビューや公式コメントをもとに、芥見が語ってきた言葉の数々を整理し、物語の根底にある考え方を読み解いていきます。作品を読み返す上で、創作の裏側を知る手がかりになるでしょう。
アニメをもう一度振り返りたいときは、
こちらからすぐにチェックできます。
芥見下々の創作観──インタビューから浮かび上がる作品の軸
芥見下々の発言を丁寧に追うと、物語づくりの中心に「人間の感情」を置くという姿勢が一貫していることが分かる。『呪術廻戦』では、負の感情が呪霊として形を取り、人間と呪いがぶつかり合う世界が描かれているが、この設定自体が“感情の扱い方”を物語の土台に据えているという指摘は多い。
公式ファンブックなどで芥見は、自作には“既視感が多い”と自覚的に語っている。これは偶然ではなく、先人の作品が築いた“型”に向き合ったうえで、自分の解釈を加えるという姿勢から生まれたものだと説明されている。 影響を受けた漫画が非常に多いことを認めつつ、「王道をきちんと描く」ために必要な選択だという考えも語られている。
作品の語り口においては、設定や意図を過剰に説明しないことが特徴的だ。キャラクターの行動や台詞の背景をすべて言語化せず、読者が読み取る余地を残す。それによって、倫理観や価値観が揺れるような場面が生まれやすく、批評でもこの“余白を意識した作り”が作品に独特の緊張を与えていると分析されている。
負の感情を否定せず、むしろ“あるもの”として扱う姿勢も芥見らしい。恨みや妬みが呪霊になる世界観は、敵と味方を単純な構図に分けない。人間の側にも醜い部分があり、それが呪いを生むという重い視点がインタビューや対談で語られてきた。 そのため、読者は呪霊を単なる悪として解釈できず、物語の中で何度も価値観を揺さぶられる構造になっている。
さらに、芥見は週刊連載に求められる“速さ”に敏感だ。体調不良による休載が発表された際には、編集部から以前から休載を提案されていたものの、「スピード感のない連載に魅力を感じない」「早く物語を描き切りたい」という思いから見送ってきたと振り返っている。 しかし単発の休載では改善が難しいと判断し、今回まとまった休載を受け入れたという。体調は大病ではないこと、読者を待たせることへの申し訳なさを強く感じていることも率直に語っていた。
これらの言葉を踏まえると、芥見下々は“型を理解して物語を積み上げる作家”であると同時に、“人間の感情から逃げない作家”でもある。作品を動かすのはキャラクターの選択であり、その積み重ねの奥にある感情の揺れこそが、『呪術廻戦』の重さと説得力を生み出している。
影響源と再構築の手法──どの作品が『呪術廻戦』に息づいたのか
芥見下々は、自作について“既視感が多い”と自覚的に語ってきた。これは偶発的なものではなく、幅広い作品から受けた刺激を踏まえたうえで、「王道に向き合う」という創作姿勢に基づいた選択だとインタビューで説明されている。
影響源としてしばしば名前が挙がるのが、久保帯人『BLEACH』や冨樫義博『HUNTER×HUNTER』である。公式ファンブックの対談では、『BLEACH』の影響を受けたことを率直に認めながら、作家性の強い部分を表面的に模倣する危険性を語り、意図的に距離を取ってきたという姿勢も紹介されている。また、小学生の頃に『BLEACH』第1話を読んだ経験が漫画家を志すきっかけになったと語ったことも伝えられている。
能力体系に関しては、冨樫作品からの影響を本人が明確に言及している。公式ファンブックのQ&Aでは、影響を受けた作家として冨樫義博と奈須きのこを挙げ、呪術の仕組みに“縛り”を設ける考え方が『HUNTER×HUNTER』の「制約と誓約」を下敷きにしていると話している。また、キャラクターを作る際に細かな背景や価値観を整理するプロセスについては、『Fate』シリーズの奈須きのこの手法に触発されたと説明されている。
こうした影響の“明示”は、作中のオマージュとしても現れている。たとえば0巻2話の障子越しの場面は『新世紀エヴァンゲリオン』のゼーレ会議の演出を引用したものだと解説されており、1巻1話の構成には『BLEACH』第1話や『NARUTO』の影響が混ぜ合わせられていると語られている。
漫画以外の分野でも影響は広い。芥見はホラー作品への造詣が深く、平山夢明『他人事』でジャンルに惹き込まれ、ジャック・ケッチャム『オフシーズン』などを愛読書として挙げている。映画ではタランティーノ『パルプ・フィクション』、ノーラン『インターステラー』、さらには伊丹十三『マルサの女』を扉絵でオマージュするなど、参照範囲がジャンルを超えて広がっている。加えて『ザ・レイド』シリーズの格闘描写がバトルシーンに反映されていると語ったことも紹介されている。
アニメ作品では『新世紀エヴァンゲリオン』への強い敬意が明かされている。ファンブックのインタビューでも庵野秀明作品に対する好意が語られ、ロボットアニメでは『エヴァ』のほか『コードギアス』『エウレカセブン』への言及も見られる。心理描写とアクションを同時に成立させる群像劇的な構図に惹かれている様子がうかがえる。
ただし、芥見はこれらの要素を“そのまま使う”のではなく、王道バトル漫画の文法に合わせて再構築している。ジャンプの創作講座では、キャラクターの初登場シーンで瞬時に印象を与える重要性や、対立構図の組み立て方などを語っており、自らの手法を若手作家に向けて整理して説明している。
こうして多様な影響を素材として取り込みながら、自作の文脈に合わせて組み替えていく。その積み上げが、『呪術廻戦』特有の“どこか覚えがあるのに、次の展開が読めない構造”を生み出していると言える。
“呪い”というテーマの扱い方──負の感情を物語へ変える視点
『呪術廻戦』では、呪霊が「人間の恐怖や怒り、嫉妬といった負の感情から生まれる存在」として語られている。これは作品の基本的な世界設定として明確に示されており、呪術師たちは、人が生み出したその影と向き合う役割を担っている。 物語を解説する記事でも、呪霊を“負の感情の蓄積が形となったもの”として説明し、呪術師との対立構造を作品全体を貫く軸として位置づけている。
この設定によって、“呪い”は単純な敵ではなく、人の心の弱さやしんどさが外側に現れた存在として描かれる。外部の批評では、作中で繰り返される悲劇──たとえば吉野順平のエピソードのように、追い詰められた人物が抱えた怒りや復讐心が悲しい結末へつながる構図──が象徴的な例として取り上げられている。 その分析では、「人を呪わば穴二つ」ということわざになぞらえ、感情の行き場を失った結果が呪いとなり、最終的には自分自身を傷つけてしまうという循環が指摘されている。
さらに同じ批評では、宿儺が特級呪霊・漏瑚に向けた言葉にも触れられている。宿儺は漏瑚の動機を否定しながらも、その最期には「誇れ」「オマエは強い」という言葉をかける。この場面について、呪霊を完全な悪として断罪するのではなく、一つの存在として向き合う姿勢があると読み解かれている。
こうした描写を通して浮かび上がるのは、“呪い”が物語の中で負の感情の象徴として機能しているという点だ。呪術師たちが立ち向かうのは怪物ではなく、社会や個人の中に生まれる感情の歪みであり、その感情をどう扱うかがキャラクターたちの選択に重ねられていく。
直接的にテーマを語るインタビューは多くないものの、作品の設定やキャラクターの物語から読み取れるのは、負の感情を否定するのではなく、それがどのように生まれ、どう向き合うかを描こうとする姿勢である。『呪術廻戦』に漂う重さや深さは、こうした感情の扱い方そのものに根ざしている。
キャラクターはこう生まれる──芥見下々が語った構築法
芥見下々は、キャラクターづくりに関してかなり具体的な考えを示しており、集英社の「少年ジャンプ漫画賞ポータル」では審査員として複数の講座に参加している。その中で語られる内容から、芥見のキャラクター観はかなりはっきりと読み取れる。
まず重視されているのは「初登場の一瞬で何者かが伝わるか」という点だ。「初登場から印象に残るキャラクターの作り方」をテーマにした講座では、姿勢や間の取り方、置かれた状況の切り取り方によってキャラクター性が自然に伝わる構図の大切さが語られている。外見を凝るよりも、その人物がどう立ち、どう振る舞うかに“性格が宿る”という考え方が前提になっている。
さらに、キャラクターは“単体で成立する存在”としてではなく、「物語の中でどの役割を果たすか」から逆算して作られている。講座「芥見先生の脳内領域展開!! ~呪術廻戦ができるまで~」では、キャラの作り方とネーム構築が実務的に説明され、物語の流れの中でどの場面に配置するかを前提に性質を決めていくやり方が紹介されている。
また、キャラクターの設定を過度に盛り込まないという姿勢も特徴的だ。公式ファンブックには350問以上のQ&Aが収録され、膨大なキャラクター設定が記されているが、作中ではそのすべてを語ることはしない。必要な情報だけを必要な場面で提示し、語られない部分は読者に委ねる――その距離感が意識されている。
行動原理の一貫性についても、芥見は強い関心を示している。「キャラクターを行動させるときに大事なポイント」を扱った回では、キャラクターの意思決定を先に固め、それを外さない形で動かす重要性が語られている。人物の判断がぶれないことで、読者が“なぜそう動くのか”を理解しやすくなり、物語自体の説得力も増すという考えだ。
こうした発言の積み重ねから見えてくるのは、芥見下々がキャラクターを 登場の瞬間の印象・物語上の役割・行動の一貫性 という複数の視点で組み立てている作家だということだ。細かな設定だけでキャラクターを支えるのではなく、読者がページをめくるごとに性格や価値観が立ち上がるような“動き”を重視している。その手法は、作品全体の緊張感やキャラクターの魅力にそのまま反映されている。
完結後に語られた本音と、新章『Modulo』への挑戦
『呪術廻戦』は2018年の連載開始から6年半にわたり展開され、2024年9月の本誌で物語を締めくくった。単行本最終30巻は同年12月に発売され、描き下ろしのエピローグとともに作者の率直なあとがきが掲載された。
このあとがきで芥見下々は、自身を「未熟な漫画家」と位置づけ、「6年半、約7年間ひり出した結果、よく分かったのは自分が本当に馬鹿だった」という強い言葉を綴っていると複数の報道が紹介している。 さらに、作品を通じて“傷ついた人へ何かできればと思って描いてきた”という心情にも触れており、本作が作者にとって精神的な負荷の大きい創作であったことがうかがえる。 終盤では、「どんな理由であれ読んでくれた人に感謝します。またどこかで」と読者への感謝を述べ、物語に区切りをつけている。
連載中には体調不良による休載もあり、2021年の休載発表時には、芥見自身が直筆メッセージで「休載期間は1か月ほど」「大きな病気ではない」と説明した。その際、編集部から以前から休みを勧められていたものの、週刊連載の“スピード感”を失いたくなかったため踏み切れなかった、と理由を語っている。 しかし、単発の休みではスケジュールを立て直せないと判断し、まとまった休載を受け入れた経緯も伝えられている。
そんな本編完結から約1年後の2025年9月、芥見は新たなスピンオフ『呪術廻戦 Modulo』の原作として再び動き始めた。本作は作画を岩崎優次が担当し、短期集中連載として位置づけられている。 連載発表時のコメントで芥見は、『Modulo』について「コンパクトなシリーズ」と説明し、「打ち切られなければ半年ほど、単行本3冊程度」を想定していると語ったと報じられている。
『Modulo』は、本編の「死滅回游」から68年後の2086年を舞台にした作品で、乙骨憂太や禪院真希の子孫が登場する“時間の飛躍”を用いた構成が特徴とされる。 公式の発表では、「国際的な呪術事情」「日本外の呪術師」「人類と異質な存在」がテーマとして掲げられており、本編では描かなかった領域に踏み込む試みが示されている。
本編の世界を“そのまま継ぐ”のではなく、時間軸を大きくずらした上で別視点から呪術世界を再構成する方式を選んだのは、過去インタビューでも語られた“自作の矛盾を避けつつ新しい要素を試したい”という姿勢とも一致している。
最終巻のあとがきで見せた厳しい自己評価、連載中の迷いと責任感、そして完結後にあえて別角度から世界を広げようとする姿勢。その流れを見ると、芥見下々にとって創作は一区切りでは終わらず、むしろ完結という節目を使って“次に何を試せるか”を模索し続ける営みであることがよく分かる。
まとめ──作者の言葉が指し示す“呪術廻戦”の本質
芥見下々の発言をたどっていくと、『呪術廻戦』という作品が偶然の積み重ねではなく、作者が抱える価値観や創作姿勢の集合体であることが分かる。負の感情を軸に据えた世界観、王道に向き合いながら既視感を意図的に取り込む手法、キャラクターの行動原理を重視した構築法――それらはどれも、作品全体に漂う緊張感の源となっている。
また、芥見は創作に対して常に厳しい視線を向けている。連載中の休載コメントではスピードへのこだわりと読者への責任感が語られ、最終巻のあとがきでは自己評価の低さや葛藤が率直に示された。完結後に『呪術廻戦 Modulo』へと踏み出した姿勢からは、世界観を別の角度から再構築しようとする意欲も読み取れる。
こうした言葉の積み重ねは、芥見下々が描く物語が“呪い”や“負の感情”を単なる設定ではなく、人間の生き方そのものに結びつけて捉えていることを示している。作品の奥にある揺らぎや不安、救いのあり方は、作者自身が向き合い続けてきた問いの延長線上にあり、その視点こそが『呪術廻戦』をただのバトル漫画では終わらせない大きな要因になっている。
完結した現在もなお、芥見下々が残した言葉は作品の理解を深める手がかりとなり、新しい呪術世界の広がりを予感させる。創作の迷いと意志、その両方が『呪術廻戦』という物語を支える根幹であり、今後の挑戦にもつながっていく。