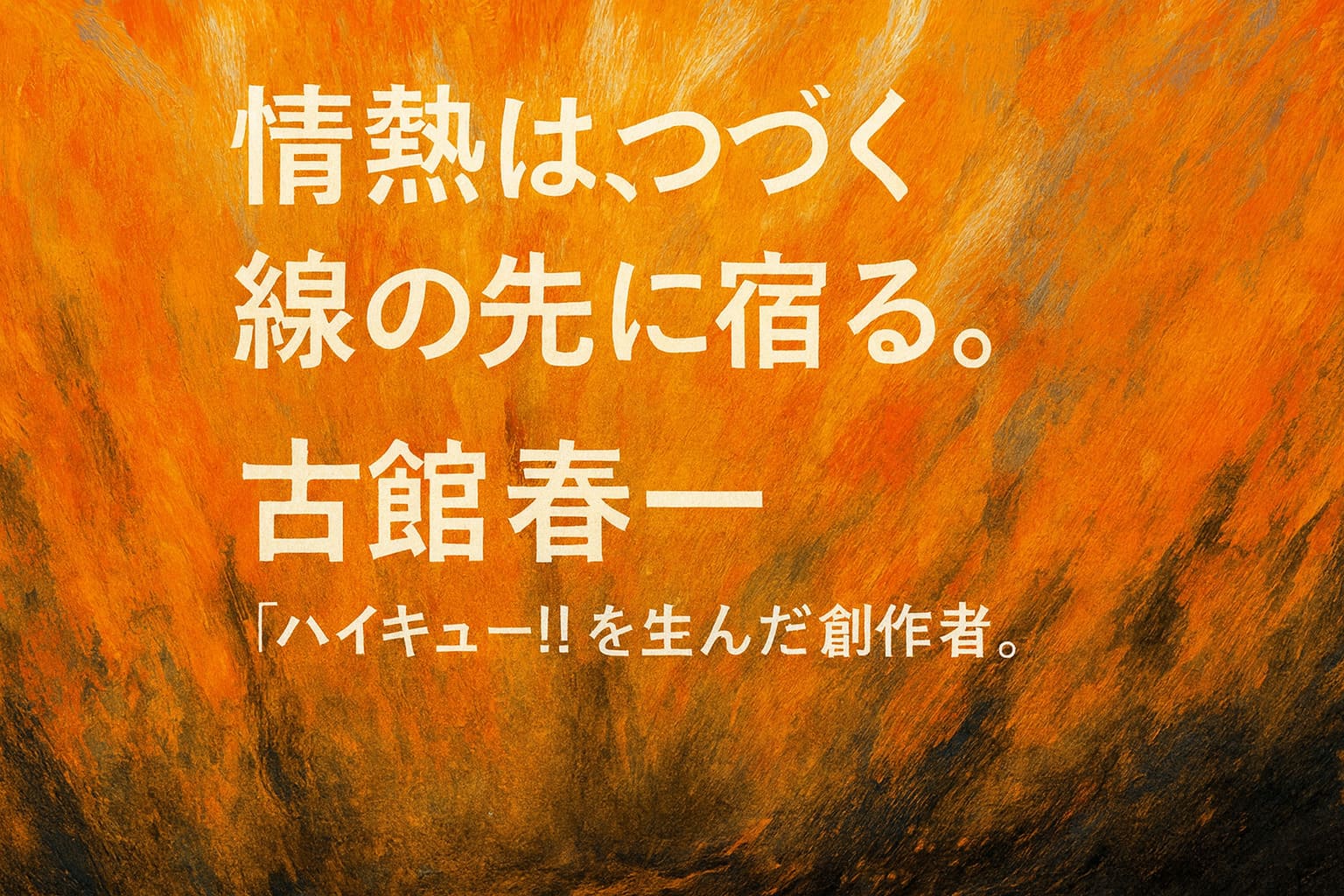『ハイキュー!!』を描いた古舘春一は、どんな経験を重ねてあの青春と熱量の物語を生み出したのか。
学生時代のバレーボール部での葛藤、社会人生活を送りながら地道に続けた創作活動、そして作品の裏側で積み重ねてきた取材の姿勢──そのすべてが、躍動感あふれる試合シーンと等身大のキャラクターたちにつながっている。
本記事では、古舘春一という創作者の歩みと、『ハイキュー!!』誕生までの背景を丁寧にひも解いていく。
ハイキュー!!作者・古舘春一とはどんな人物なのか
古舘春一は、岩手県軽米町生まれの漫画家で、代表作『ハイキュー!!』によって国内外で幅広く知られる存在となった。高校卒業後は宮城県のデザイン専門学校に進み、さらにデザイン会社で働きながら漫画の創作を続けていたという異色のキャリアを持つ。社会人として経験を積みつつ、地道に持ち込みや応募を重ねた結果、ジャンプの新人賞を獲得し、そこから本格的に漫画家としての道が開けていった。
中学・高校ではバレーボール部に所属し、練習環境に恵まれない中で必死に競技に向き合った経験がある。作中の空気感や、努力や挫折を丁寧に描く姿勢は、この実体験が土台となっている。部活に懸けた時間や当時の悩みが、キャラクターたちの心理描写にも自然と反映されているのが特徴だ。
デビュー後しばらくはホラー作品を描いており、静けさや緊張感の“間”を巧みに使う表現はこの時期の影響が大きい。『ハイキュー!!』ではスポーツ漫画でありながら、独特のテンポや緊張の演出にその名残が見られる。本人はインタビューに多く登場するタイプではないが、少ない発言からは作品づくりへの姿勢の真面目さや、徹底した取材を欠かさない姿がうかがえる。
派手な自己表現よりも作品を前に出すタイプの作家であり、その静かな情熱が『ハイキュー!!』という大きな物語の核になっていると言える。
古舘春一の学生時代のバレー経験と創作への影響
古舘春一は、中学・高校の6年間をバレーボール部として過ごした。強豪校ではなかったため思うように結果が出せず、「もっと伸ばせたのでは」という思いを抱えたまま卒業したと語っている。この“やり切れなかった感覚”がのちに創作の原動力になり、バレーを題材にした漫画を描く決意へとつながった。
当時のポジションはミドルブロッカー。クイックが決まった瞬間の気持ち良さや、セッターとの呼吸が合う瞬間の高揚感は、作中の攻撃シーンに色濃く反映されている。本人は「自分が感じたあの一瞬を漫画で表現したかった」と語っており、日向と影山の連携が物語の軸になったのも、実体験が深く関係している。
また、練習の空気やチーム内の距離感、うまくいかない時間のつらさなど、部活動で誰もが経験するリアルな心情が作品の随所に描かれている。勝つ楽しさだけでなく、焦りや迷いまで丁寧に描写されているのは、作者自身がバレーに真剣に向き合った過去を持つからこそ生まれたものだ。
こうした背景が、『ハイキュー!!』に特有の“部活特有の温度”を与え、読者が思わず自分の青春時代を重ねてしまうようなリアリティを支えている。
古舘春一が漫画家として歩み始めるまで
古舘春一が創作の道に踏み出したのは、高校卒業後に進んだ仙台デザイン専門学校で学んだ時間と、その後の社会人経験が大きく関わっている。デザインの基礎を学び、広告制作会社で実務に携わりながら、視線誘導やレイアウトの組み立てといった技術を身につけた。これらの経験は、のちの漫画表現──ページ全体の構図やコマの配置、見せ場の作り方──にそのまま活かされている。
一方で、心の中心にはずっと「バレーボール漫画を描きたい」という思いが残り続けていた。仕事の合間を縫って制作した作品を持ち込み、新人賞に応募する日々を続け、2008年に『King Kid』でJUMPトレジャー新人漫画賞の佳作を受賞。この受賞が、編集部との本格的なやり取りへとつながる最初の大きな転機となった。
その後、読切の制作や打ち合わせを重ね、『アソビバ。』(2009年『赤マルジャンプ』掲載)で商業誌デビュー。さらに同年、週刊少年ジャンプに掲載された読切『詭弁学派、四ツ谷先生の怪談』が評価され、2010年には同作を基にした連載が始まった。ここで得た緊張感の演出やコマ運びの技術は、後の『ハイキュー!!』にも深く影響している。
こうして、デザインの現場で培った技術と、地道な投稿活動で積み重ねた経験が合わさり、古舘はジャンプ作家としてのキャリアを確かなものにしていった。
初期作品とホラー志向のルーツ
古舘春一が本格的に商業誌で活動を始めた頃、その作風は現在の『ハイキュー!!』とは大きく異なり、むしろ“学園ホラー”が中心だった。最初に読者の前に姿を見せたのは、2009年に『赤マルジャンプ2009 WINTER』へ掲載された読切『アソビバ。』で、これが公式にデビュー作として扱われている。
同年には、週刊少年ジャンプ本誌に『詭弁学派、四ッ谷先生の怪談』を読切として発表。この読切が評価され、2010年には同作を原型とした連載『詭弁学派、四ッ谷先輩の怪談。』が始まった。明確なホラージャンルで、学校を舞台にした怪異と、核心の部分を語り過ぎない“余白”の使い方が特徴の作品だった。
この時期の表現で特に際立っていたのが、緊張を高めるための“間”の置き方や、ページをめくる瞬間に向けて視線を誘導する構図作りだ。恐怖を直接的に示すのではなく、読者に「不穏さ」をじわりと感じさせる技法は、のちにスポーツ漫画へ転じても色濃く残っている。
実際、『ハイキュー!!』の中には、試合の流れが突然変わる瞬間や、コートに漂う空気が一変する場面が多く描かれるが、こうしたメリハリのある演出には、初期のホラー作品で身につけた技術が自然と活かされていると指摘される。初期作で培われた表現の幅は、後の代表作にとって重要な土台となった。
『ハイキュー!!』誕生と制作の舞台裏
『ハイキュー!!』が生まれた背景には、古舘春一自身が抱えていた「もう一度バレーボールに向き合いたい」という強い思いがある。学生時代に味わった悔しさや、うまくいかない時間の中で抱えた感情を、今度は“物語として形にしたい”と考えたことが出発点になったと語られている。
物語の軸となるのが、セッターとスパイカーが一瞬で呼吸を合わせるコンビプレーだ。古舘はミドルブロッカーとしてプレーしていた経験から、クイックが決まる瞬間の感覚に強く惹かれており、「あの一撃の気持ちよさをどうしても漫画で表したかった」と話している。日向と影山の関係性や“変人速攻”の発想は、まさにこの体験が土台になっている。
作品の舞台となる宮城県の景色や体育館の空気感には、作者が東北で過ごした日々の記憶がさりげなく反映されている。地方校ならではの距離感や、冬場の体育館の温度差など、言葉で説明されない細かな空気が画面から伝わるのは、作者自身の生活の記憶が溶け込んでいるからこそだ。
制作にあたっては、実際のチームや指導者への取材を重ね、選手の思考や競技の“流れ”を丁寧にすくい上げることを大切にしていた。取材した内容をそのまま描くのではなく、物語として最も熱が伝わる形に再構成する姿勢が、一つひとつの試合の緊張感を支えている。
実体験と綿密な取材、その両方を軸に組み上げられた『ハイキュー!!』は、リアルさと読みやすさを両立した作品として、多くの読者に支持される存在となった。
古舘春一の取材スタイルと作品づくりのこだわり
古舘春一の創作姿勢を語るうえで欠かせないのが、丁寧な取材と、それを漫画として最適な形に組み直す独自の方法だ。バレー経験者でありながら、自身の記憶だけに頼らず、実際のチームや指導者に話を聞き、練習や試合の空気を現場でつかもうとする姿勢が一貫している。担当編集者も「雑談の中から必要な情報を自然に引き出すのがとても上手い」と評価しており、選手の心理や勝負の流れといった目に見えない部分まで丁寧に拾い上げている。
ただし、集めた情報をそのまま紙面に移し替えることはしていない。本人は「リアルに寄りすぎると物語の動きが鈍り、逆に演出を優先しすぎると競技としての説得力が薄れる」と語っており、現実とフィクションのバランスを常に意識している。技術や戦術は実際に存在するものを土台にしつつ、物語として最も熱が伝わる形に再構成する──この調整力こそ、古舘の作品づくりの大きな特徴といえる。
コマ割りや構図も非常に綿密で、「大ゴマと小ゴマの限界を探るつもりでページを組んでいる」と語ったことがある。試合の緊張感を高める場面では細かなコマを連ねてリズムをつくり、勝負が動く瞬間には大胆な見開きで一気に視界を開く。こうした視線誘導の巧さは、デザインの現場で培ったレイアウトの感覚とも結びついている。
セリフの運びにも無駄がなく、説明的になりすぎないよう細心の注意が払われている。長い語りよりも、短くまっすぐな一言に感情の核を込めるスタイルを重視しており、その姿勢は作品全体のテンポにも影響している。
このように、綿密な取材と、漫画としての最適化を両立させる手法が、リアリティと読みやすさを併せ持つ『ハイキュー!!』の強さを支えている。どのエピソードにも“競技の熱”が宿っているのは、古舘春一の一貫したこだわりの積み重ねによるものだ。
『ハイキュー!!』完結後の古舘春一の現在と今後の展望
『ハイキュー!!』が2020年に完結してからも、古舘春一は定期的に創作の場へ戻り続けている。完結後しばらくは新連載を立ち上げていないが、決して表舞台から離れたわけではなく、『ハイキュー!!』関連の読み切りやコラボ企画、新作の短編など、活動の幅を広げながら制作を続けている。
2022年には、Vリーグとのコラボマッチを題材にした読み切りが週刊少年ジャンプに掲載され、原作完結後の世界が描かれたことで大きな反響を呼んだ。さらに2023年には、学習マンガ誌「勉タメジャンプ」で犬と英語をテーマにした新作『犬えいご!!』をスタート。従来の作風とは異なる柔らかいタッチでの挑戦となり、「ハイキュー!!の作者による“絵本的アプローチ”」として注目を集めた。
また、劇場版『ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』公開に合わせ、イベント用の新規イラストを描き下ろすなど、作品世界とのつながりも途切れていない。2025年には、スポーツメディア「Sportiva」のバレーボール特集号で高橋藍選手のイラストを担当し、表紙・裏表紙を飾るなど、バレーボール分野とのコラボレーションも継続している。
このように、現在の古舘春一は“長期連載は控えながらも、常に描き続けている”状態と言える。次にどのジャンルへ挑むのかはまだ明かされていないが、新たな作風にも積極的に取り組んでいる様子から、いずれ大きな動きがあるのではと期待されている。
作者の歩みを知ると、もう一度『ハイキュー!!』を観返したくなるものです。
作品の熱量をそのまま感じたい方は、こちらから今すぐ視聴できます。
DMMプレミアムはバナーをタップ👇