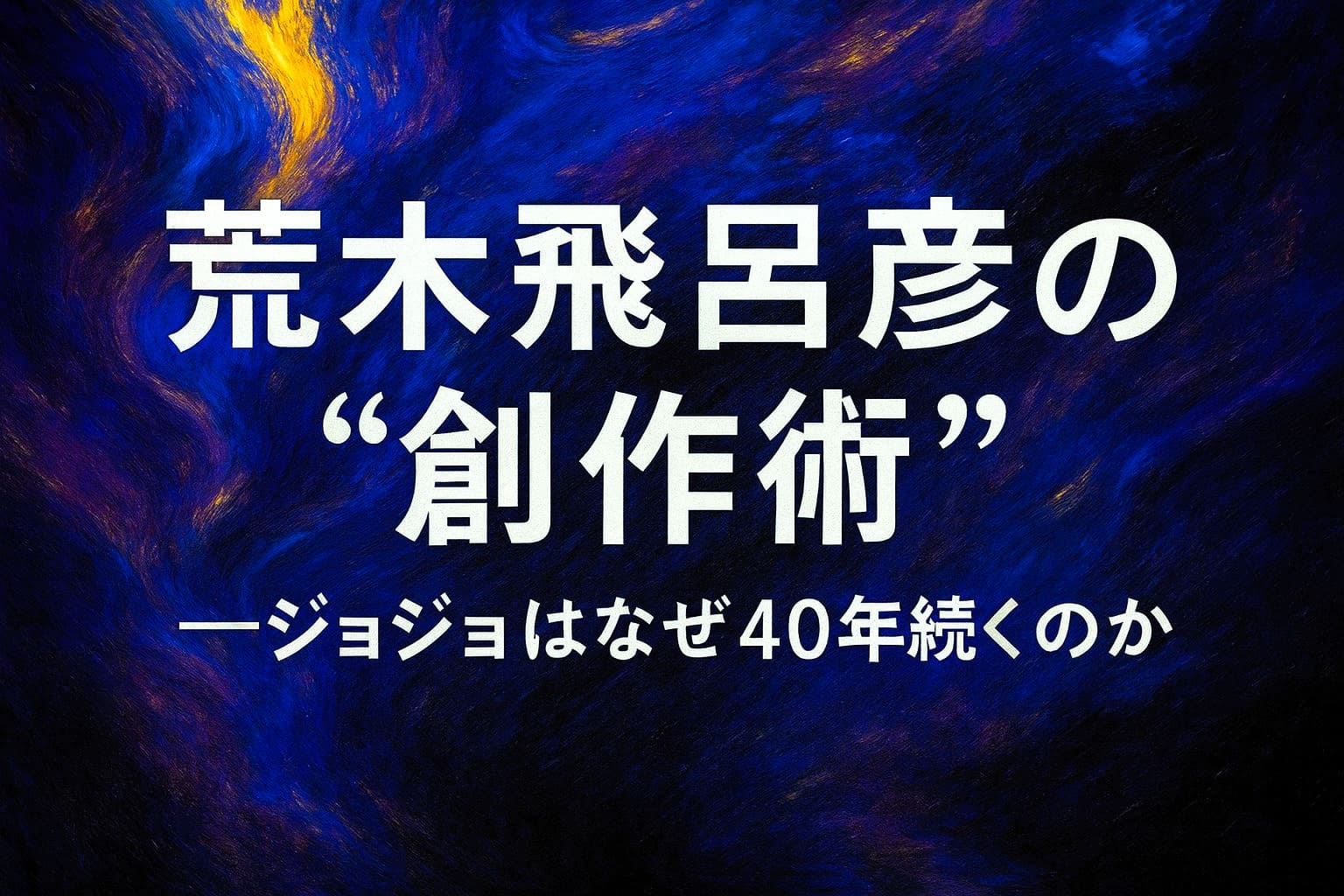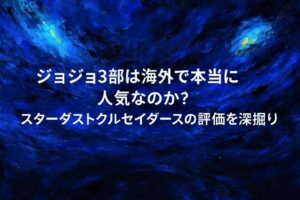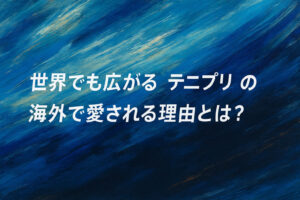荒木飛呂彦が40年にわたり描き続けてきた『ジョジョの奇妙な冒険』には、奇抜な表現の奥に一貫した創作の姿勢がある。大胆なポーズ、緻密な構図、強烈なキャラクター──そのどれもが思いつきではなく、日常の観察や美術への関心、そして綿密な設計によって支えられている。本記事では、過去の著書やインタビューを手がかりに、荒木の創作がどのように組み立てられ、なぜ長く読み継がれてきたのかを紐解いていく。
荒木飛呂彦が貫いてきた“創作の軸”とは
荒木飛呂彦の作品を振り返ると、どれだけ時代が移っても、その根底に流れる思想が変わっていないことに気づく。個性的なキャラクターや突飛に見える設定の奥には、必ず一本のテーマが通っており、それが作品世界を支える支柱になっている。
荒木が繰り返し語ってきた「人間賛歌」は、単なる前向きなスローガンではない。誰かに解決してもらうのではなく、自分の意志と選択で運命を切り開く姿を描くという考え方に根ざしている。物語の中で偶然が主人公を助ける展開が少ないのは、キャラクター自身の覚悟や行動によって前へ進む姿を大切にしているからだ。どの部でも“どう生きるか”が問われる構図になっているのは、まさにこの哲学の表れと言える。
また、ジョジョの“奇妙さ”が読者を置き去りにしないのは、荒木が設定や能力に必ず理由づけを行っているためでもある。キャラクターの性格や過去と、行動や能力が自然につながるように作られているため、どれほど非現実的な場面でも説得力が保たれる。大胆でありながら筋の通った世界観は、この姿勢によって生まれている。
派手なビジュアルと静かなテーマ性を同時に成り立たせること。その二つを矛盾させず作品に落とし込む姿勢こそが、荒木飛呂彦の創作を形づくる揺るぎない核であり、長く読み継がれてきた理由にもつながっている。
発想の源泉──観察と美術から生まれるアイデア
荒木飛呂彦の発想は、思いつきではなく“観察”を起点にして積み上げられている。作品の舞台となる場所を描く際には、可能な限り現地に足を運び、人の動きや空気、そこで暮らす人々の姿を丁寧に見る。どんな場面を描くにしても、まず「何が本当に必要か」を自分の目で確かめる姿勢があり、その過程で得た感覚がキャラクターの佇まいや街の風景へ自然に反映されていく。
観察の対象は日常だけではない。荒木は古典絵画や彫刻、写真、映画といった幅広い表現から刺激を受けてきたと語っており、とくに西洋彫刻の身体のひねりや古典絵画の構図は、キャラクターのポーズやページの構成に大きく影響している。ファッションのエッセンスを取り込むことも多く、布の流れや装飾の線がキャラクターに“美しい動き”を与える要素として、しばしば活かされている。
音楽や映画から受ける影響も大きい。制作中に流す音楽をシーンによって変えたり、映画のカット割りを参考にアクションの流れを組み立てたりと、漫画以外の分野から得た感覚を積極的に創作へつなげている。こうした異なるジャンルの刺激が作品全体のテンポや空気感を形づくり、ジョジョ独特の“リズム”を生んでいる。
日常の観察、美術への関心、他ジャンルからの刺激――これらを漫画として機能する形に再構成することで、ジョジョの奇妙で美しく、どこか説得力のある世界観が生まれる。荒木飛呂彦のアイデアは突発的なひらめきではなく、継続的な観察と深い興味を創作へ変換する確かな手法によって支えられている。
物語は“結末から逆算して”作られる
荒木飛呂彦は、物語づくりに明確な“芯”を置くことを重視している。著書『荒木飛呂彦の漫画術』で示される「キャラクター・ストーリー・テーマ・世界観」という四つの柱は、その物語の軸となる部分であり、ここが定まっていれば展開が大きくぶれないと語っている。物語の行き先を先に描き、そこへ向かう道筋を考えるという姿勢は、長期連載でも筋が通る理由のひとつと言える。
また、荒木は“悪役の目的”を深く掘り下げることを重要視している。新書『新・漫画術 悪役の作り方』では、物語を支えるのは主人公だけではなく、敵側の信念や理屈の強さだと位置づけており、敵の美学が明確であるほど、主人公の選択にも説得力が生まれるとしている。悪役が単なる妨害役ではなく、自分なりの理由を持って動いていることが、ジョジョの緊張感を支える要素になっている。
さらに、展開に“偶然の救い”を持ち込まない点も特徴的で、インタビューでも登場人物が自分の意志と行動で状況を切り開く物語を好むと語られることが多い。ご都合主義ではなく、どんな結果に至るかよりも「どう戦い、どんな判断をしたか」に焦点を置くことで、極端な設定の中でも物語に筋が通り、読者が納得できる流れが生まれている。
物語の芯を先に描き、悪役の目的を固め、偶然に頼らない。こうした考え方の積み重ねが、長く続くシリーズであっても荒木作品に一貫した緊張感と説得力を与えている。
絵柄の進化は止めない──変化し続ける表現へのこだわり
荒木飛呂彦の絵柄は、時代によって大きく形を変えてきた。デビュー当初の『魔少年ビーティー』や初期の『ジョジョ』では、当時主流だった劇画調の影響が強く、太い線や深い陰影、マッチョな体格が目立つスタイルが採用されていた。荒木自身も、人気アクション俳優の肉体を参考にしたことを明かしており、力強い体つきや迫力ある構図は、その時代の感覚を反映していたと語られている。
やがて、絵柄は大きく変化していく。インタビューや講演では、古典絵画や西洋彫刻から強い影響を受けたことが繰り返し語られており、特にイタリアで見たベルニーニの彫刻の動きやねじれたポーズが衝撃的だったと振り返っている。 人物の体のひねり、動作の流れ、布がまとわりつくような線の扱いは、こうした美術作品の観察から取り込まれたものだ。
色彩や衣装の面では、ファッションや写真の影響が色濃い。カラー原稿では補色の組み合わせで画面に強いエネルギーを持たせる方法が紹介されており、服装のデザインにはハイファッション的な要素が多く見られる。これは対談記事や制作解説でも触れられており、雑誌のルックやブランドの造形美を漫画的に再構成する手法として語られている。
こうした変化の背景には、“より良い描き方を求める”という姿勢が一貫してある。荒木は決して現在の絵柄に安住せず、人体の美しさや動きの説得力をどう表現するかを探り続けてきた。ジョジョの大胆なポーズは奇抜さが話題になることも多いが、実際には人体の立体感を強調するための構図であり、美術的な観察から導かれたものだと説明されている。
このように、荒木の絵柄の変遷は流行に合わせた変化ではなく、表現を磨き続ける過程そのものだ。その積み重ねによって、原画展や海外展示で作品が“アート”として扱われる機会も増えており、絵柄が年を経ても古びないと言われる理由にもつながっている。
生活と仕事のリズムが創作を支える
荒木飛呂彦の創作スタイルをたどると、派手なエピソードよりも「生活リズムを崩さない」という地味だが堅実な姿勢が目立つ。漫画家というと徹夜続きの不規則な生活を想像しがちだが、インタビューや特集では、規則正しく起きて仕事をし、夜はきちんと休むというリズムを意識していると紹介されることが多い。長期連載を続けるうえで、無理な働き方ではなく“続けられるペース”を優先しているということだ。
食事や運動についても、極端な健康法ではなく「描き続けるための体調管理」という位置づけが一貫している。量を抑えた食事や、日常的な運動の習慣が若々しさの理由として取り上げられることはあるが、本人の言葉を辿ると、それは見た目のためというよりも、仕事のパフォーマンスを維持するための工夫として語られている。結果的に「老けない漫画家」として話題になる一方で、その根っこにはシンプルな生活の整え方がある。
制作現場の体制についても、徹夜前提のスケジュールではなく、時間を区切って集中することを重視していると伝えられることが多い。アシスタントに無理をさせるのではなく、一定のリズムで仕事が回るように組み立てることで、連載が長期化してもクオリティを保ちやすくなる。これは、創作を“気合い”だけに頼らず、仕組みとして安定させようとする考え方と言える。
特別な秘訣があるわけではなく、「生活のリズムを乱さない」「体調を大きく崩さない」という基本を守り続けること。その積み重ねが、何十年にもわたって第一線で描き続ける力になっている。華やかな作品の裏側にある、静かな規律こそが、荒木飛呂彦の創作術を支えるもう一つの柱になっている。
ページ構成と演出──読者を迷わせないための技術
ジョジョの独特な迫力や奇妙さは、奇抜なポーズやスタンド能力だけで成り立っているわけではない。荒木飛呂彦は、ページ全体の“読みやすさ”をどこよりも重視しており、その姿勢は著書や講義、過去の取材でも繰り返し語られてきた。視線の流れを丁寧に設計し、どのコマからどこへ目を誘導するかを徹底的にコントロールする。これがあるからこそ、どれほど複雑な戦闘でも読者が迷わず物語に入り込める。
アクションシーンでは特に、キャラクターの位置関係や動きが直感的に理解できるよう工夫されている。派手な見せ場を大きなコマで配置し、その前後の動作を補うコマを丁寧に並べることで、スピード感の中にも“わかりやすさ”が保たれる仕組みになっている。大胆な構図が多いにもかかわらず混乱が起きないのは、この視線誘導の精密さによるものだ。
さらに荒木は、ページの“間”の使い方にも強いこだわりを持っている。キャラクターが静かに状況を見つめる一瞬や、空気が変わる場面にあえて余白を置くことで、読者の感情が自然に切り替わるように調整している。戦いの緊迫感や不穏さは、この“間”によって増幅される。
擬音の扱いも特徴的だ。ジョジョの「ゴゴゴゴ…」に代表されるように、擬音が背景の一部として存在感を持ち、空気や気配までも視覚化する。音という概念を文字で表すのではなく、シーン全体の雰囲気を構成する要素としてページに組み込んでいるのが荒木流だ。
こうした細やかな設計が積み重なることで、ジョジョの奇抜な世界はただ派手なだけではなく、読者を迷わせない“強い読み物”として成立している。視線の流れ、間、擬音――それらすべてを計算し尽くしたページ構成こそ、荒木飛呂彦の演出力を支える重要な技術と言える。
荒木飛呂彦が語る“創作の哲学”──40年描き続けるための視点
荒木飛呂彦の創作術を語るうえで欠かせないのが、作品そのものだけでなく、“作り手として何を大切にするか”という哲学だ。過去の対談や著書から読み取れるのは、華やかな発想の裏に、驚くほど実直で地に足のついた考え方があるということだ。
荒木は、作品のテーマを「人間の持つ力」「困難を乗り越える意志」など、普遍的なものに置くことを重要視している。奇抜な設定や能力があっても、物語の芯となる“人間賛歌”が揺るがないため、読者はどの部から読んでもキャラクターの信念を感じ取れる。同時に、時代に合わせて題材を変えつつも、核となる価値観を変えない姿勢が、シリーズを通して共通した強度を生み出している。
また、荒木は「漫画は文化であり芸術である」という意識を強く持っている。単に娯楽として描くのではなく、美術史や文学、映画など、幅広い領域の知識を積極的に吸収し、作品のエネルギーに変換していく。“漫画の外”の視点を取り入れることが、ジョジョに独自の深みや立体感を与えている。
さらに特徴的なのは、「作風を守るのではなく、進化させ続ける」という姿勢だ。デビュー時の画風や構成に固執せず、時代や自身の興味に合わせて積極的に変化させる。技術的にも価値観的にも“止まらない”ことが、40年にわたって作品が古びず、常に新鮮さを保つ理由につながっている。
創作に対してストイックであることと同時に、意外なほど軽やかでもある。完璧さを求めるのではなく、「まず描いてみる」「試して合うなら続ける」という柔らかい姿勢が、長期連載の中で新しい発想や挑戦を生み出してきた。
荒木の創作哲学は、奇抜な世界観とは裏腹に極めて堅実で、そして柔軟だ。“人間を描くこと”を中心に据えながら、変化と挑戦を続ける。そのバランスこそが、ジョジョという作品を特別な存在にしている。
▼記事で興味が深まった方へ
ジョジョ全シリーズや関連映像は、DMMプレミアムでまとめて楽しめます。
荒木飛呂彦の創作を、実際の映像で体感してみてください。
荒木飛呂彦の“創作術”が教えてくれること
荒木飛呂彦の創作論を振り返ると、表現の派手さよりも「作品を支えるための土台づくり」が一貫して重視されていることがわかる。著書『荒木飛呂彦の漫画術』で示される「キャラクター・ストーリー・テーマ・世界観」の4本柱は、その象徴だ。物語の芯を最初に固めることで、長期連載であっても展開に無理が生じにくく、読者が迷わず作品の軸をつかめる構造が作られている。
キャラクターについては、性格や行動原理、細かな癖まで整理した“身上調査書”を用意する方法が紹介されており、登場人物の説得力を強める基礎として活用されている。 特に悪役は、続編『新・漫画術 悪役の作り方』で「物語の強度を決める存在」と位置づけられ、彼らの信念や目的を深く掘り下げることが作品全体の緊張感につながると語られている。
絵柄の変遷については、古典絵画や彫刻、ファッションといった多様な領域からの影響を取り入れ、よりよい表現を求めて更新を続けてきたことがインタビューで繰り返し語られている。初期の劇画調から現在の洗練された線へと変化したのは、流行に合わせたのではなく、表現を磨き続けた結果だった。
生活面でも、荒木は「無理をしない働き方」を大切にしていると特集記事で紹介されている。徹夜を前提としない作業リズムや、日常的な体調管理が、長い連載を支える現実的な基盤になっている。
そして、「漫画でしか表現できないものに挑む」という姿勢も特徴的だ。コマ割り、擬音、間の取り方といった技術は、荒木が“漫画の言語”として重視してきたもので、単なる装飾ではなく読者の体験そのものを形作る役割を担っている。
奇抜な世界観の裏側には、綿密な設計と静かな規律、そして変化を恐れない柔軟さがある。これらの積み重ねが、ジョジョを年代を超えて読み継がれる強い作品へと押し上げている。