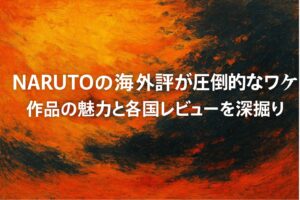NARUTOの物語が幕を閉じ、忍の世界が平和を迎えたその先には何があったのか。
続編である『BORUTO』は、戦乱を知らずに育った次世代の視点から、“平和の重さ”と“受け継がれる意志”を描き出す物語です。
主人公うずまきボルトは、偉大な父・七代目火影ナルトという存在を前に、自分自身の価値をどこに見いだすのか悩みながら成長していきます。
科学忍具の普及、価値観の変化、新たな脅威の台頭──。
世界は見た目以上に揺らぎながら前へ進んでいます。
本記事では、作品全体の流れ、主要キャラクターの役割、最新章「TWO BLUE VORTEX」の動き、そして海外での反応まで、BORUTOの本質を分かりやすくまとめて解説します。
BORUTOとは?物語の基本と世界観の全体像
BORUTOは、『NARUTO -ナルト-』で描かれた第四次忍界大戦の終結後、忍の世界にいったんの平和が訪れた時代を舞台にした続編シリーズです。主人公は七代目火影となったうずまきナルトと日向ヒナタの長男・うずまきボルト。ナルトが里を率いる立場になった一方で、ボルトは“火影の息子”という重い看板と向き合いながら、自分自身の生き方を探っていくことになります。
木ノ葉隠れの里は、高層ビルや大型モニター、鉄道網が整備された近代的な街へと変貌しており、かつての戦乱を知る世代から見るとまったく別の景色が広がっています。忍の里であることに変わりはないものの、科学忍具をはじめとした技術革新が進み、忍の役割や“強さ”の意味そのものが問い直されている世界です。原作スタッフも、この作品世界を「平和だが再び混乱に脅かされる、冷戦期のような状況」にたとえて言及しています。
こうした環境の中で、ボルトは同世代の仲間たちと共に忍者アカデミーに通い、後に新生第七班の一員として任務にあたります。ナルト世代のキャラクターたちは親や上司となって登場し、かつての英雄が日常の中で抱える葛藤や責任も物語の背景として描かれます。平和な時代に育った子どもたちが、戦争を直接知らないがゆえに抱く価値観の違いと、親世代とのずれが、BORUTOならではのドラマを生み出しています。
総じてBORUTOは、「ナルトの息子の物語」というだけでなく、戦後の世代が受け継いだ世界をどう理解し、自分なりの答えを見つけていくかを描く作品です。NARUTOから続く“意思を継ぐ”というテーマを土台にしながらも、親子関係や技術と伝統のせめぎ合いなど、現代的なテーマを前面に押し出した続編として位置づけられています。
物語の背景──平和後の忍の世界と時代の変化
BORUTOの全体像を理解するためには、まず「漫画」と「アニメ」で展開の仕方が大きく異なる点を押さえておく必要があります。どこまでが第1部で、どこから第2部なのかという区切りも明確なため、ここを整理しておくと作品全体を追いやすくなります。
漫画『BORUTO -ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』は、2016年に週刊少年ジャンプで連載が始まり、その後2019年からはVジャンプへ移籍しています。原作・脚本を担当した小太刀右京から、物語後半では岸本斉史へと引き継がれ、作画は一貫して池本幹雄が担当。第1部は全20巻相当で2023年4月に一区切りとなり、同年8月からは第2部『BORUTO -TWO BLUE VORTEX-』として新章がスタートしています。物語は数年後の世界が舞台になり、ボルトやカワキの立場にも大きな変化が生まれています。
テレビアニメ版『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』は、2017年4月にスタートし、2023年3月に放送された第293話で第1部が終了しました。アニメは漫画以上に日常描写や学校生活を丁寧に描く回が多く、キャラクター同士の距離感や関係性がわかりやすく描かれているのが特徴です。第293話以降は“第2部制作が決定している状態での休止”となっており、再開時期は正式発表を待つ段階にあります。
時系列としては、アカデミー期から新生第七班の活動が始まる序盤、第1部後半の「殻(カラ)」や“楔(カーマ)”、大筒木一族に関わる物語、そして数年後を描く第2部『TWO BLUE VORTEX』へと続きます。BORUTOはこのように明確な二部構成となっており、それぞれでテーマや雰囲気、ボルトを取り巻く状況が大きく変化していく点が、シリーズを見る上で重要なポイントになっています。
主要キャラの役割と関係性──ボルト世代の特徴
BORUTOはNARUTOの正式な続編でありながら、物語のテーマや世界の見え方が大きく変化しています。そのため、「どこがNARUTOらしく、どこがBORUTOならではなのか」を整理しておくと、作品の特徴がよりはっきりと見えてきます。
NARUTOでは、戦争や差別といった“負の歴史”が物語の根底にあり、登場人物たちは過去を乗り越えるために戦いました。一方のBORUTOは、戦争が終わったのちの時代を舞台にしているため、物語の出発点が根本的に異なります。平和の中で育った世代は、親世代とはまったく別の価値観を持ち、戦いそのものを前提としていません。この価値観の断絶が、作品に独自の緊張感を与えています。
また、世界観にも大きな変化があります。木ノ葉の里は大規模な開発が進み、鉄道や高層ビルが並ぶ近代都市へと姿を変えました。この環境は、いわゆる“忍者の世界観”とは遠ざかったようにも見えますが、同時に、科学忍具をはじめとした新しい技術によって“忍とは何か”を問い直す展開を生んでいます。伝統的な忍術だけで戦ってきたナルト世代と、技術と共に育つボルト世代の間に生じる価値観のギャップこそ、BORUTOの柱となるテーマの一つです。
さらに、作品の中心となるテーマにも違いがあります。NARUTOが“自分の存在意義を求める物語”であったのに対し、BORUTOは“偉大な父を持つ子供が自分自身の答えを探す物語”として描かれています。ナルトが「認められたい」という思いで走り続けたのに対し、ボルトは「最初から認められていることの重さ」と向き合わなければならない。この対比が、親子二世代を軸にしたドラマを際立たせています。
こうした“つながり”と“違い”が共存することで、BORUTOは単なる後日談にとどまらず、現代的な悩みや世代間の断絶を扱う、まったく新しい物語として成立しています。それでもなお、ナルトが掲げた“意思を継ぐ”という精神は作品の中心に息づいており、NARUTOから続く物語であることを強く印象づけています。
科学忍具と新時代の技術──旧世代とのギャップ
BORUTO第1部は、ボルトが忍者アカデミーを卒業し、サラダ、ミツキと共に新生第七班の一員として本格的に任務へ出るところから大きく動き出します。序盤では、仕事に追われる火影ナルトへの反発や、「火影の息子」として見られることへの苛立ちが前面に出ており、父への複雑な感情がボルトの行動原理になっています。その一方で、チューニン試験や強敵との戦いを通して、ボルトは仲間と力を合わせることの意味を少しずつ学んでいきます。
物語の転機となるのが、大筒木モモシキとの戦いと、その後に刻まれる“楔(カーマ)”です。モモシキは死の間際にボルトへ謎の印を残し、やがてそれが大筒木一族の“バックアップ”として機能する特殊な力であることが明かされます。楔は宿主の肉体を書き換え、術の吸収や大幅な戦闘能力強化をもたらす一方で、本人の存在そのものを脅かす危険な刻印でもあります。
中盤以降は、「殻(カラ)」という組織と、彼らが“器(うつわ)”として扱ってきた少年・カワキの登場によって、物語のスケールが一気に広がります。ボルトと同じく楔を持つカワキは、戦いの末に木ノ葉に保護され、ナルトの家に身を寄せることになります。共同生活の中でボルトとカワキは反発し合いながらも次第に心を通わせ、ボルトの家族観や「里を守る」という意識にも変化が生まれていきます。一方で、殻の首魁ジゲン(イッシキ)がナルトやサスケと激突し、その過程でナルトが新たな変身「バリオンモード」を発動し、九喇嘛(クラマ)との別れに直面するなど、親世代の物語も大きく動きます。
第1部終盤では、楔をめぐる危機が頂点に達し、ボルトの体を乗っ取ろうとするモモシキの存在と、ボルトを“脅威”と見なしたカワキの決断が正面からぶつかります。アニメ第293話にあたるエピソードでは、カワキがボルトを殺すという衝撃的な展開を迎え、モモシキの力によってボルトは辛うじて生還するものの、二人の関係も物語全体の空気も決定的に変化していきます。この「さよなら」の場面が第1部の大きな区切りとなり、数年後を描く第2部『TWO BLUE VORTEX』へとバトンが渡されます。
大筒木の脅威と新たな敵──物語を動かす根幹設定
第2部『BORUTO -TWO BLUE VORTEX-』は、第1部のクライマックスから数年後の世界を舞台にした物語です。舞台は引き続き木ノ葉隠れの里ですが、物語の前提が大きく反転しており、ボルトとカワキの立場もかつてとはまったく違うものになっています。第1話の時点で、ボルトは指名手配される立場となり、里の外から動く“ならず者のような存在”として描かれます。一方で里に残ったカワキは、火影ナルトの保護者のような立場で振る舞い、里側からは“正しい側”として受け止められています。
この立場の逆転は、物語上の能力「全能(オムニシエンス)」によって、世界中の人々の記憶や認識が改変された結果だと説明されています。改変後の世界では、「ナルトの息子」としての立場がボルトからカワキへとすり替えられ、ボルトは“ナルトを危機に陥れた人物”として扱われています。その中で、うちはサラダやスミレといった一部の人物だけが改変の影響を受けず、元の歴史を覚えている存在として描かれ、物語の倫理的な軸を支える役割を担っています。
第2部では、新たな脅威として大筒木に関係する存在が複数登場し、忍界全体に広がる異常事態が描かれ始めます。尾獣の行方や、木ノ葉の外で暗躍する勢力の動きなど、世界規模の不穏な変化が示され、ストーリーのスケールは第1部以上に拡大しています。それに呼応するように、ボルト自身の戦い方も変化しており、刀を用いた接近戦と楔の能力を組み合わせたスタイルで、かつての少年期とは異なる“歴戦の忍”としての姿が強調されています。
物語の中心に据えられているのは、やはりボルトとカワキの対立構造です。ただし、第2部で描かれるのは単純な善悪の衝突ではなく、それぞれが「ナルトを守る」「世界を守る」と信じる方向性の違いから生じる対立です。第1部冒頭で暗示されていた、成長したボルトとカワキが木ノ葉の廃墟で対峙するシーンに向けて、物語は少しずつ“なぜそこまで関係がこじれてしまったのか”を埋めていく流れになっています。
このように、第2部『TWO BLUE VORTEX』は、第1部で積み上げた人間関係と設定をあえて反転させるところから始まり、ボルトの新たな覚悟と世界規模の危機を同時に描く章へと移行しています。物語はまだ連載途中で先行きは不透明ですが、シリーズ冒頭から示されていた“ボルトとカワキの決定的な対立”へ向けて、着実に地ならしが進んでいる段階だと言えます。
親子のすれ違いと成長──ナルトとボルトの関係性
BORUTO第2部では、主要キャラクターの立場と関係性が大きく変化しています。とくにボルト、カワキ、サラダの三人は物語の軸となる存在であり、それぞれが別の方向へ進みながらも、見えないところで深くつながっています。
まずボルトは、記憶改変の影響で里から追われる立場になったことで、かつての仲間とは距離を置きながら行動しています。幼い頃の無邪気さは消え、単身で危険な地域を動く姿には、忍としての覚悟と緊張感が色濃くにじんでいます。一方で、完全な孤独というわけではなく、危機に備えて動き続ける中で、彼なりに里や家族への思いを抱え続けていることも示されています。
対してカワキは、ナルトを守るという一点に全てを捧げた結果、記憶改変後の世界では“火影の息子”という立場に収まっています。彼は自分を拾ってくれたナルトを救うために行動しているものの、その信念は強すぎるがゆえに周囲を巻き込む危うさも帯びています。ボルトとカワキの対立は、互いの価値観がぶつかり合う必然の結果でもあり、物語を引っ張る大きなエネルギーとなっています。
サラダは、記憶改変を受けずに元の歴史を知っている数少ない人物です。周囲からの理解を得られない状況でも、ボルトを信じ続ける姿勢は揺らいでいません。火影を志す彼女にとって、正しいと思うことを貫く責任がさらに重くのしかかり、感情よりも意志が前面に出る場面が増えています。その成長は、物語が進むほど際立つテーマのひとつです。
このほかにも、ミツキやシカダイといった仲間たちは、それぞれの立場で“変わってしまった世界”に向き合っています。誰が正しく、誰が間違っているのかが単純に判断できない状況だからこそ、彼らの判断や迷いがストーリーに奥行きを与えています。
第2部のキャラクターたちは、もはや子どもではありません。立場の違い、価値観の衝突、守りたいものの優先順位が明確になってきたことで、彼らの選択は物語の行方を左右する重さを持ち始めています。こうした関係性の変化は、BORUTOが続編でありながら独自の物語として成立している大きな理由のひとつです。
BORUTOが描く“受け継がれる意志”と世代の価値観
BORUTOという作品を語るうえで欠かせないのが、「受け継がれる意志」というテーマの継続と変化です。NARUTOが“戦乱の時代に生きる忍の成長”を描いた物語だとすれば、BORUTOは“平和を維持するために何を選ぶのか”という新しい問いを提示する作品になっています。
ナルト世代は、争いが常態化した世界で育ち、命のやり取りを通じて仲間との絆や信念を深めていきました。彼らの価値観は戦火の中で形成され、その痛みが火影としての責任感にもつながっています。一方でボルト世代は、平和が当たり前の社会で生まれ育ち、「戦争を知らない世代」という特徴を持っています。それは恵まれた環境でありながら、同時に「努力しなければわからない現実」でもあります。
その違いは、父と子のすれ違いとして作品の中心に描かれています。ナルトにとって火影の仕事は、誰かを守るための当然の行為ですが、ボルトにとっては「家にいてほしい父親の代わりに仕事ばかりしている存在」に映ります。ナルトが背負ってきた“世界を守る責任”と、ボルトが求める“家族としての距離感”は、本来は相反するものではないはずですが、立場や経験の差によって大きな溝を生み出しています。
さらに、BORUTO第2部では、ナルト世代が物語の中心から一度退くことで、“若者が何を受け継ぎ、どこへ向かうのか”がより鮮明に描かれるようになりました。親から子へ、師から弟子へ、価値観や信念がどのように引き継がれ、時代に合わせて変化していくのか。これは続編であるBORUTOが独自に掘り下げている重要なテーマでもあります。
結局のところ、BORUTOは「ナルトの世界のその後」を描くだけの作品ではありません。平和の時代に生まれた世代が、過去の価値観をどう解釈し、新しい時代の在り方を模索する物語です。戦争の記憶を知らないからこその迷いや葛藤、そして成長。こうした世代間の対比こそが、BORUTOが長年愛され続ける理由のひとつになっています。
第2部TWO BLUE VORTEXの展開と今後の焦点
BORUTOの物語は、第2部「BORUTO -TWO BLUE VORTEX-」に入り、大きく方向性が変わりました。穏やかな日常を描いた序盤とは対照的に、緊張感の高い展開が続き、世界観そのものが再構築されつつあります。
物語の中心には、ボルトとカワキの“立場の入れ替わり”が据えられています。この出来事は、単なるストーリー上の仕掛けではなく、「受け継ぐ者」と「継がれる世界」の関係を問い直す役割を担っています。ボルトは追われる側となり、これまでとは逆の視点から世界を見ることを余儀なくされました。それにより、彼が戦う理由や信じるものが、これまで以上に明確になっていきます。
また、大筒木の脅威は消えたわけではなく、むしろ新しい局面を迎えています。第2部では、旧世代では太刀打ちできなかった存在と向き合うことになり、その緊迫感が物語を大きく動かしています。父の世代が戦ってきた“過去の呪い”と、次世代が向き合う“新たな脅威”。この落差が、BORUTOならではのダイナミックな世界観を形作っています。
第2部のボルトは、少年時代の未熟さを残しながらも、仲間を守るために自立した選択を迫られています。その姿は、かつてのナルトが歩んだ道を思わせる部分がありながら、まったく異なる価値観の上に築かれています。だからこそ、続編でありながら別物の作品として魅力を発揮しています。
今後の展開は、仲間との再会、大筒木の動向、そしてボルト自身の“選ぶ未来”が焦点になると考えられます。物語のテーマはよりシンプルになり、同時に深みを増していくでしょう。BORUTOは、ナルトの遺伝子を受け継ぎながら、次の時代に何を託すのか。その答えが、これからの物語の中で丁寧に描かれていくはずです。
BORUTO世界の広がり──国際関係と世界観の再構築
BORUTOシリーズが高く評価される理由の一つに、NARUTOから受け継いだ世界観を維持しながら、新しい価値観や文化を積極的に取り入れている点があります。第1部では、科学忍具や新たな忍術体系が登場し、忍の技術が現代的にアップデートされました。これは単なる設定変更ではなく、“忍の世界が平和を迎えたあと、どう発展するのか”という必然的な変化として描かれています。
第2部「TWO BLUE VORTEX」では、世界観がよりシリアスな方向へ舵を切り、これまで描かれなかった“外の世界”の影響が色濃く反映されています。忍五大国だけが中心だったNARUTOに対し、BORUTOではより広域の国際関係が重要な要素となり、物語の視野が格段に広がっています。
世界観の継続性という点では、木ノ葉隠れの里や火影制度など、NARUTOから続く“根幹の部分”は維持されています。その一方で、一部の制度や価値観は新時代に合わせて変化しており、里の内部でも“旧世代と新世代の意識差”が作品のテーマとして描かれています。
特に、親世代が築いた平和は“受け継ぐ努力”なしには維持できない、というメッセージは、BORUTOの世界観の重要な軸になっています。これは、戦いの舞台が変わっても、登場人物が置かれている状況が変化しても、作品が持つ精神性をつなぎとめる役割を果たしています。
BORUTOの世界はこうした連続性と新しさが自然に共存しており、これが読者にとって“続編でありながら新しい作品”として受け入れられ続ける理由のひとつになっています。
親世代からの継承と次世代の葛藤
BORUTOの根底には、父と子の関係を通して描かれる“価値観の世代交代”があります。NARUTOが親を知らずに育ち、孤独の中で仲間と絆を築いたのに対し、ボルトは愛されて育ってきたからこそ、父が抱えてきたものを理解しきれないという対比が物語の要です。
ナルトは火影としての責任と父としての役割を両立しようとしますが、その努力がボルトにとっては“家にいない父”として映り、すれ違いを生みます。このすれ違いは単なる家庭の問題ではなく、“平和の中で何を守るべきか”という世代の価値観の差を象徴しています。
その一方で、物語が進むにつれて、ボルトは父が背負ってきたものの大きさを少しずつ理解し、ナルトもまたボルトが抱える葛藤に気づいていきます。完全に同じ価値観にはならなくても、互いに理解し合おうとする姿勢が、親子の成長として丁寧に描かれています。
第2部ではナルトが物語の表舞台から一度退いているものの、ボルトの選択や行動には常に“父の影響”が色濃く残っています。ナルトの生き方をそのままなぞるのではなく、そこから何を受け取り、どう変えていくのか。そのプロセスこそがBORUTOという作品の魅力であり、NARUTOから自然につながるテーマでもあります。
ボルトが“父を超える瞬間”はいつ来るのか。その答えはまだ描かれていませんが、親子が互いに影響を与えながら進んでいく姿こそが、BORUTOが続編として確かな存在感を持つ理由のひとつになっています。
BORUTOの海外人気が分かれる理由と各国の評価
BORUTOは世界中で視聴されている作品ですが、その受け止められ方には国ごとに微妙な差があります。NARUTOが“どこの国でも圧倒的人気”という揺るぎない存在だったのに対し、BORUTOは視聴者層・文化・世代交代のタイミングによって評価が割れやすい傾向があります。
まず、北米・欧州では「NARUTOの続編」として期待が極端に高く、序盤の落ち着いた物語運びに対して“静かすぎる”“刺激が少ない”という声が上がりやすい一方、親子関係や現代社会的なテーマが深まる中盤以降は評価が反転し、キャラクターの成長や政治的な背景に対する肯定的なレビューが増えています。
アジア圏では、NARUTO世代のファンが非常に厚いため、「世代交代による作風の変化」そのものを楽しむ層と、「NARUTOの雰囲気をもっと残してほしい」という層に分かれる傾向があります。とくに技術の進歩や戦闘の価値観の変化は、国によって賛否が大きく動くポイントになっています。
一方で、中東・南米は若年層のアニメ視聴者がとても多いため、ボルト世代のキャラクター像やスピーディな展開を好む声が多く、新章に入ってからのアクション重視の作風が高く評価される傾向があります。
結果的に、BORUTOは国ごとに“どの部分を魅力と感じるか”が大きく違う作品として受け止められています。それはマイナスではなく、視聴文化やファン層が多様化した現代において、シリーズが広い層にアプローチしている証でもあります。NARUTOでは描かれなかった新しい価値観が、海外での議論をさらに活発にし、作品の奥行きを深める要因にもなっています。
NARUTOからBORUTOへ受け継がれる物語の総まとめ
BORUTOは、単に「NARUTOの続編」という一言では片づけられない独自の役割を担っています。戦争の時代を描いたNARUTOと、平和の時代を舞台にするBORUTOでは、物語の目的もキャラクターの視点も根本的に異なります。それでも両作を貫くテーマは共通しており、それが“受け継ぐ意志”という精神です。
NARUTOでは、孤独の少年が仲間と絆を築き、世界を平和へ導くまでの過程が描かれました。BORUTOは、その平和がどのように維持され、次世代がどんな価値観を育てていくのかを描く物語です。二つの作品は「戦いの決着」と「平和のその後」という異なるフェーズを扱っていますが、それぞれが世界観を補完し合い、より大きな物語の全体像を形作っています。
シリーズが続くにつれて、ナルト世代とボルト世代の役割は明確に分かれ、同時に互いに影響を与え続けています。ナルトたちが築いた平和は、ボルトたちが何を選び、どう向き合うかによって形を変えていきます。それは、物語が“世代をまたいで続く”ことの説得力を生み、長寿シリーズでありながら新鮮さを失わない理由にもなっています。
第2部「TWO BLUE VORTEX」に突入した現在、物語はよりシンプルでダイナミックなテーマへ向かっています。主人公の成長、仲間との再会、世界の脅威。そして“父を超えられるのか”という最も根源的な問い。そのすべてが、BORUTOという作品を次の段階へ押し上げています。
NARUTOからBORUTOへ続くこの長い物語は、単なる続編ではなく、価値観の変化を世代ごとに描く壮大な連作です。シリーズ全体を通して描かれる“意志の継承”こそが、この作品世界の核となっています。