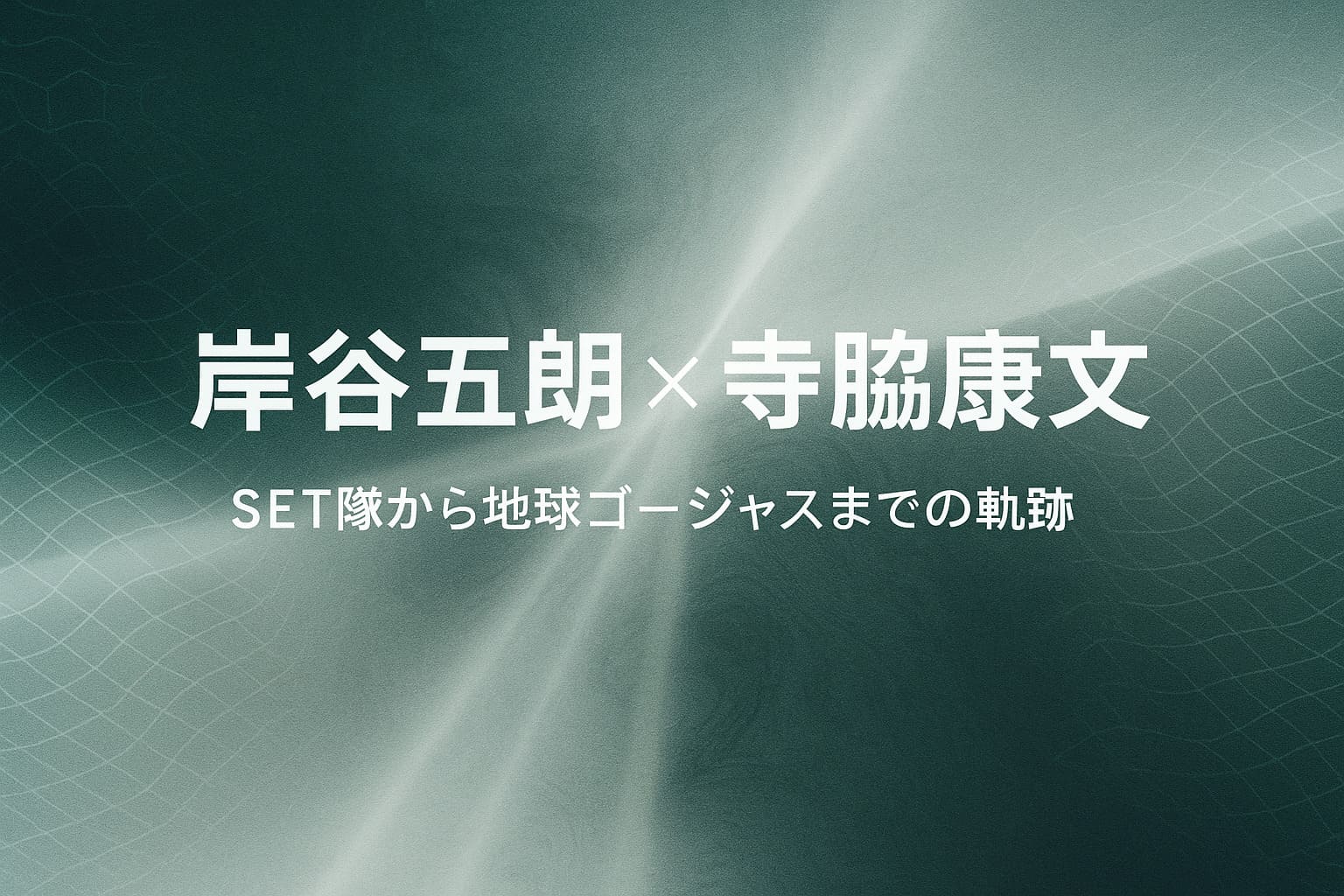岸谷五朗と寺脇康文は、1980年代に同じ劇団で活動を始めて以来、長く創作を共にしてきたパートナーだ。SET隊として舞台経験を重ね、1994年には演劇ユニット「地球ゴージャス」を立ち上げ、現在まで多彩な公演を続けている。舞台づくりの方向性や表現の捉え方に共通点が多く、互いの役割を自然に分担できる関係性が長期的な協働を支えてきた。本記事では、二人の関係の始まりから主要作品、ユニット運営の背景までを整理し、そのパートナーシップがなぜ途切れず続いてきたのかを読み解いていく。
岸谷五朗と寺脇康文の関係はどこから始まったのか
岸谷五朗と寺脇康文の関係は、1980年代前半に同じ劇団で活動を始めたことから始まる。二人が所属した劇団スーパー・エキセントリック・シアターは、芝居やコメディ、アクションなど幅広い表現を取り入れる方針を持ち、稽古量も多いことで知られていた。そこには多くの若手が集まり、岸谷と寺脇も同じ稽古場で舞台づくりに取り組む環境に身を置いていた。
稽古や小劇場公演で過ごす時間が重なるなかで、互いの芝居に対する姿勢を自然と理解するようになり、役者としての相性や呼吸の合い方が見えてくるようになる。役柄に応じて動き方や会話の間を調整する必要がある劇団スタイルは、相手の反応を細かく感じ取る技術が求められ、共演者同士の距離が近くなる土壌でもあった。
こうした環境での経験が、後に二人が共同で舞台を手がける際の土台となった。劇団時代に積み上げた感覚が共通言語となり、創作の方向性や演出面で意見のすり合わせがスムーズに進む基盤がすでにできていたともいえる。特に寺脇が俳優として現場を支え、岸谷が全体の構成や演出に視点を持つという役割は、この頃から自然に定まっていった。
劇団での活動を通じて信頼関係が深まり、互いの表現への理解が進んだことが、1994年の演劇ユニット結成へとつながっていく。二人が長年にわたり協働を続ける関係性の原点は、この劇団での時間にある。
SET時代に築かれた岸谷五朗と寺脇康文の基盤
岸谷五朗と寺脇康文が本格的に同じ舞台で活動するようになったのは、1980年代前半に劇団スーパー・エキセントリック・シアターで過ごした時期である。劇団では演技だけでなく、ダンスやアクションまで含めた総合的な稽古が組まれており、日々のトレーニングを通じて役者としての体づくりと表現の幅を自然に広げていった。こうした環境で過ごすうちに、二人は互いの動き方や感覚を共有しやすい関係になり、舞台上で合わせるための共通言語が芽生えていく。
劇団の活動と並行して、岸谷・寺脇・山田幸伸の三人で構成されたユニット「SET隊」でも舞台に立った。1987年に始まったこのユニットは、劇団公演内のコントや小規模企画を担当し、観客と近い距離でテンポの良い掛け合いを求められる場だった。ここで磨かれた即応性やリズム感は、二人が後に共同で舞台作品を手がける際にも重要な役割を果たすことになる。
SET隊の活動はコメディ色が強く「お笑い的」と見られることもあったが、実際には劇団での表現力を鍛える場として機能していた。役者同士のタイミングを細かく合わせる必要があり、岸谷と寺脇が互いの癖や呼吸を正確に把握するきっかけにもなった。舞台の状況に応じて動きを変える柔軟さは、この時期に養われたものといえる。
そうした積み重ねの先に、より自由な表現を求めたいという思いが二人の間で共有されるようになる。劇団で鍛えた技術と共通の感覚を生かし、新しい創作の場を自分たちで作る方向へ気持ちが向かっていった。1994年、二人がSETを離れたのはその流れの延長にあり、後に演劇ユニット「地球ゴージャス」を結成する決断へとつながっていく。
地球ゴージャス結成に至る二人の歩みと選択の背景
1994年、岸谷五朗と寺脇康文は同じ劇団で培ってきた経験をもとに、自分たちの企画で舞台を立ち上げる道を選んだ。そこで発足したのが演劇ユニット「地球ゴージャス」である。劇団として固定メンバーを抱えるのではなく、作品ごとに必要なキャストを迎え入れる形式をとったのは、内容に応じて公演の規模や演出を変えられる柔軟さを重視したためだった。
ユニットの運営は、岸谷が全作品の演出を担う体制で始まり、脚本を手がける公演も多い。寺脇は俳優としてステージに立ちながら、制作面にも関わるという役割を担い、舞台づくりを支える立場にあった。この分担は劇団時代に形成された互いの得意分野を踏まえたもので、二人の創作過程に自然となじむ形だった。
地球ゴージャスの公演は、音楽やダンス、アクションなど複数の要素を組み合わせたエンターテインメント性の強さが特徴である。身体表現を求められる場面が多く、劇団時代の経験がそのまま舞台構成に反映されているといえる。作品ごとに異なるテーマを扱いながらも、公演全体に通底する空気感は二人の考え方に基づいており、ユニットとしての色がはっきり表れている。
旗揚げ公演となった1995年の「瓶詰の地獄」以降も、内容に応じて客演を招きながら新作を続けてきた。毎公演で座組が変わる形式は、出演者や観客に新鮮さをもたらす一方で、創作側には高い調整力が求められる。しかし、岸谷と寺脇が劇団時代から積み重ねてきた共通の感覚があるため、この仕組みを長く維持できている。
結成以来、地球ゴージャスの活動は途切れることなく続いている。自由度の高いユニット形式を選んだことは、作品ごとに新しい挑戦を取り込むための土台となり、今も二人の創作の中心に据えられている。
岸谷五朗×寺脇康文の主要共演・共同作品まとめ
岸谷五朗と寺脇康文の活動は、同じ劇団で培った経験を軸にしながら、ユニット公演や舞台制作を中心に長く続いてきた。二人が重ねてきた仕事を振り返ると、SET隊としての活動、地球ゴージャスの公演、舞台関連のメディア出演という三つの領域に整理できる。
SET隊時代の活動を振り返る
| 年代 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 1987 | SET隊として活動開始 | 岸谷・寺脇・山田幸伸による劇団内コントユニット |
| 1980年代後半 | 劇団公演内のコント企画に出演 | 近い距離で観客と向き合う小規模ステージ |
| 1990年代前半 | キャンペーン企画やイベントに参加 | ラジオなど外部出演が語られることもあるが記録は限定的 |
SET隊は劇団の内部企画として動きが多く、舞台経験を積む場として二人の関係を深める役割を果たした。
地球ゴージャス公演の主なラインナップ
| 公演タイトル | 公演年 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 瓶詰の地獄 | 1995 | 初公演。演劇ユニットとしての方向性を示した作品 |
| 星の大地に降る涙 | 2009/2022 | メッセージ性の強い演目で再演も実施 |
| クザリアーナの翼 | 2014 | ダンスや音楽を大きく取り入れた華やかな構成 |
| The Love Bugs | 2016 | 群舞やファンタジー要素を組み合わせたステージ |
| その他の作品 | 継続的に上演 | ゲスト俳優を迎えるプロデュース公演形式を維持 |
地球ゴージャスでは毎公演に異なる俳優が参加するため、作品ごとに雰囲気が大きく変わる一方、演出や構成における二人の共通した感覚が全体の軸になっている。
メディア・イベントでの共演の流れ
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 舞台関連番組 | 公演の特集や宣伝企画で二人が同席する場が複数ある |
| 情報・バラエティ番組 | ユニット活動の紹介やイベント出演で共演するケースがある |
| チャリティ活動 | Act Against Anything などの支援活動に双方が関わる |
テレビドラマや映画での本格的な共演は確認されていないが、舞台公演や宣伝活動を中心に映像メディアでの共演が続いている。
二人の関係を支える継続的な創作活動
| 活動内容 | 役割 |
|---|---|
| 公演制作 | 岸谷が演出・脚本、寺脇が出演や制作協力を担当 |
| ユニット運営 | 公演準備や方針決定を共同で進行 |
| 支援活動 | 舞台とは別に社会貢献イベントへ継続的に参加 |
長い時間をかけて蓄積された共同作業の数々は、二人の創作における信頼関係の深さをそのまま示している。舞台を中心とした共作が今も続いているのは、劇団時代から積み上げてきた呼吸の一致があるからだといえる。
なぜ二人のパートナーシップは長く続いているのか
岸谷五朗と寺脇康文が共同で舞台づくりを続けてこられた背景には、長年の経験から培われた信頼と役割分担の明確さがある。劇団時代から互いの表現の癖や得意分野を理解してきたため、新しい作品に取り組む際も余分な確認を必要としない関係が築かれている。二人の会話には、相手の判断を尊重しながら創作の方向性を整える空気があり、舞台制作の現場でも自然な流れで役割が決まっていく。
岸谷は演出家として全体の構成や作品の核を組み立て、寺脇は俳優として舞台の中心を担いながら運営面でも調整役を引き受ける。この分担は地球ゴージャスの創設時から変わらず続いており、双方が無理なく力を発揮できる形が長いパートナーシップを支えている。創作に向き合う姿勢が似ている点も、活動が長期にわたって続いてきた理由の一つといえる。
公演を重ねるなかで、二人は作品づくりにおける判断基準を共有し、舞台をどう届けるかという考え方でも共通点を持つようになった。異なる視点を持ちながらも、作品をより良くするために必要な判断は自然と一致することが多く、議論が大きくぶつかる場面は少ない。これまでの経験を踏まえ、互いの強みが作品の質に直結する関係が維持されている。
地球ゴージャスの公演は、作品ごとにまったく異なるテーマを扱うが、そこに変わらず流れているのが二人の舞台表現への姿勢である。新しい挑戦を取り入れながらも、観客に届けたいものが明確であり、その方向性を共有し続けてきた点がユニットを長く支えてきた。今後も作品の幅を広げる余地があるため、二人がどのような企画を打ち出すか期待されている。
長年の協働は決して偶然ではなく、共通した価値観と創作への誠実な姿勢が積み重なった結果といえる。劇団時代から続く関係は、時間とともに強固なものとなり、現在の活動にそのまま生かされている。これからも二人による舞台は、多様なテーマを扱いながら新たな表現を模索していくことだろう。