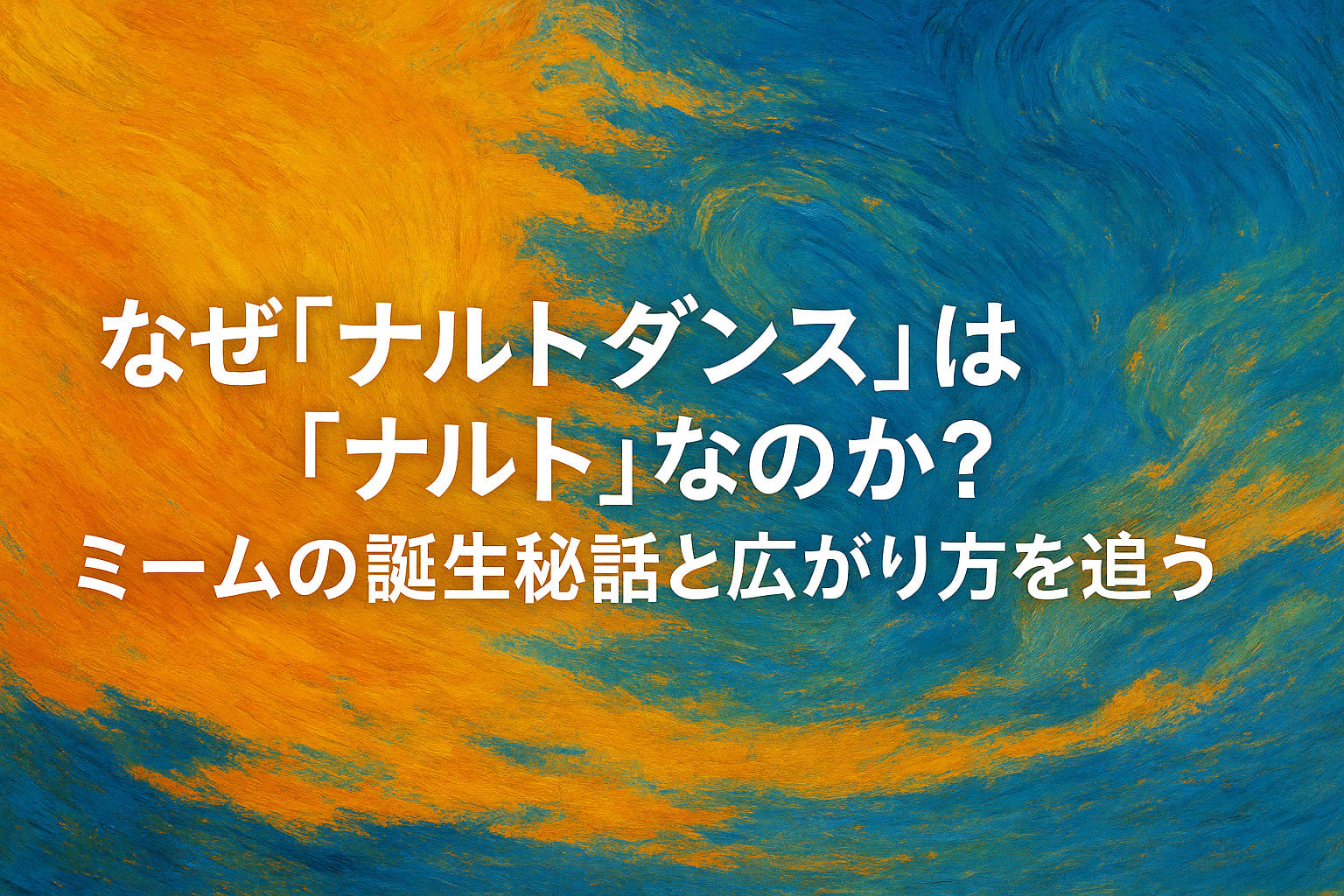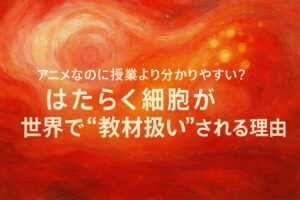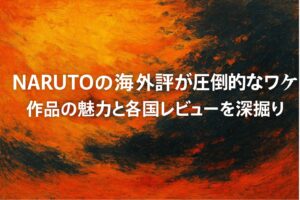SNSで突然話題に上がるようになった「ナルトダンス」。アニメの名シーンを再現した動きに見えることから、ファンの間では「どこがナルト要素なの?」「本当に原作と関係あるの?」といった疑問が飛び交っています。実はこのダンス、最初から“ナルトの公式”でも“再現ダンス”でもなく、中国のミーム文化と特定のダンス動画が混ざり合って生まれた、いわばネット文化の偶然の産物です。
いつから人々はこの動きを「ナルトっぽい」と感じるようになったのか。どんな経路で世界に広がり、曲や本家動画が拡散していったのか。本記事では、ミームの発火点から日本で定着するまでの流れを整理しながら、「なぜナルトなのか」という根本的な疑問に分かりやすく答えていきます。
はじめに:ナルトダンスはどこから生まれたのか
SNSで急速に目にするようになった「ナルトダンス」は、アニメの名場面を再現した動きとして語られることが多いものの、実際には公式作品とは直接関係のないネット発のミームです。特定のダンス動画が注目を集め、それが編集され、パロディ化され、別の文化圏へ渡って再解釈されるうちに、いつしか“ナルトっぽい”印象を持つ動きとして受け止められるようになりました。
このダンスの拡散には、短い動画でテンポよく情報が回る現代のSNS環境が大きく作用しています。動画の出どころを知らないまま共有されるケースも多く、広がれば広がるほど本来の背景が見えにくくなる現象も起きました。こうした要素が重なり、ナルトダンスは一種の“勘違いから生まれたブーム”として定着していきます。
まずは、この動きがどのような経緯で広まり、なぜ人々の目に「ナルト」に関連したものとして映ったのか。その前提を整理するところから始めていきます。
ナルトダンスはなぜ「ナルト」と呼ばれるのか
ナルトダンスという名前は、最初から付いていたものではなく、中国発のダンスミーム「科目三(Ke Mu San)」が、『NARUTO』コスプレと組み合わさって広まる過程で後から付けられた呼び名です。もともとのダンス自体は中国・広西チワン族自治区の結婚式などで踊られてきた祝いの踊りが起源で、そこに現代SNSの流行としての「科目三ダンス」が生まれ、さらにアニメとは無関係な形でブームになっていました。
転機になったのは、中国のダンサーグループ「Fz粉子(Fz Fenzi)」や「HQ cos」などが、『NARUTO』のキャラクターになりきった衣装で科目三を踊る動画を投稿したことです。忍者風のコスチュームでキレのあるステップを見せるその映像がTikTokやYouTubeショートで一気に拡散し、海外の視聴者が「ナルトのコスプレで踊っている科目三」をまとめてナルトダンスと呼ぶようになりました。
日本でも、中高生を中心にこの動画群がSNSで繰り返し共有され、「ナルトのコスプレで踊っている=ナルトダンス」というイメージが定着していきます。ニュースサイトや解説記事でも「元ネタ動画でNARUTOのコスプレをしていたことから、10代の間でナルトダンスと呼ばれている」と説明されており、公式アニメに固有の振り付けが存在するわけではないことが強調されています。
つまり、この名前は原作やアニメの設定から生まれたものではなく、「科目三ダンス」と「NARUTOコスプレ」の組み合わせに対して、視聴者側が親しみを込めて付けた通称だと言えます。
元ネタの全体像:中国ミーム「科目三」と本家動画
起源:广西(広西)発のダンス文化「科目三」
「科目三(かもくさん)」という名称は、中国の運転免許試験の第三課程を指す言葉ですが、ここから派生してダンス文化の名前としても使われるようになりました。
中国・広西壮族自治区の娯楽文化の中で、2023年10月ごろから歌曲《一笑江湖》を背景にこのダンスが短動画で急拡散。
特徴として「比較的簡易な振り付け」「繰り返し易いリズム」「誰でも模倣できるユーモア性」が挙げられ、SNS映えおよび模倣文化として拡散力を持ちました。
本家動画と踊り手
中国のショート動画プラットフォーム上には、ナルトダンス/科目三ダンスのタグ付きで多数の「踊ってみた」動画が投稿されています。たとえば「ナルトダンス 科目三 踊ってみた 一笑江湖 中国 Dance Cover」など。
これらの動画の中には、実際に一笑江湖という曲を使用しており「ナルトダンス=この科目三」がひとつの元流とされることが多いです。
ただし「ナルト公式がこの振り付けを作った」という公的証拠は見つかっておらず、「本家」とされる動画・人物も“踊ってみた系”“カバーダンス系”の区分に入ります。つまり、本家というより「最初に大きく拡散させた元動画群」が“本家扱い”されている状態です。
なぜ「ナルトダンス」と呼ばれるようになったかの流れ
- 中国で「科目三ダンス」が広がる
- 日本や海外でこの動きを見た人が、「アニメの忍者が走る動き/上体を前傾させるスタイル」を思い出し、SNSで「ナルトっぽい」とコメント
- そのまま「ナルトダンス」というタグ/呼び方が広まる
- コスプレ要素(ナルトの衣装・額あて・忍者風アイテム)を付けた動画が出始め、更に「ナルト関係」という認知が強まる
このような段階を経て、アニメ本編とは直接無関係ながら、視聴者側の認知がネーミングと結びついたと考えられます。
ポイントとして押さえておくべきこと
- 「科目三」は本来ダンス名称であり、「ナルトダンス」との関連を明文化した資料は少ない。
- 動画投稿プラットフォーム上での二次創作・模倣が元流として機能しており、“振付の起源”の特定は困難。
- 日本で「ナルト」と結びつけられたのは、視聴者の連想とSNS拡散の力によるもの。
- 本家や曲に関しても「唯一絶対の公式版」というより「複数の派生・コピー」が存在しており、流動的なミーム構造である。
この章で「元ネタ」と「本家動画および流れ」の全体像を整理しました。次章では、このミームがどう世界に広がり、日本でどのように定着したかを見ていきます。
世界的ミーム化と日本でのブーム
科目三ダンスは中国国内で火がついたあと、ショート動画文化の影響を受けて周辺国へすばやく広がりました。特に海外ユーザーの間では、踊りのテンポとコミカルな動きが受け入れられやすく、動画の編集によって個性を加える二次創作が増えていきます。背景を差し替えたり、キャラクター風の衣装を加えたり、ペットに合わせてアニメ調の加工を施したりと、元の形を残しつつも別ジャンルの遊び方へ変化したことが拡散を加速させました。
その中でも、猫や犬などの動きに合わせて科目三のステップを編集で合成した動画は再生数が大きく伸び、一気に世界に伝わるきっかけになります。人間が踊る動画とは違い、ミーム特有の「誰が見ても面白い」普遍性が働き、言語圏を問わず模倣が増えていきました。
日本に届いたのは、このペット編集動画やコスプレ風のダンス動画が海外で大量に共有された時期と重なります。とくにTikTokとYouTubeショートでリミックスが繰り返されるうちに、“ナルト風の衣装で踊る科目三”という形が目に触れる機会が増え、それがそのまま「ナルトダンス」と呼ばれる流れを作りました。
若い世代では呼び名だけが先に広まり、元の文化背景を知らないまま流行に参加するケースも多く、ミームとして独自の進化を遂げたことが日本でのブームを支えています。
こうした拡散の過程を見ると、ナルトダンスと呼ばれる現象は単なるダンスの流行ではなく、各国のユーザーが自分なりのアレンジを加えながら育てていった“国境を越えるネット文化”として成立していると言えます。
楽曲と踊りの特徴:曲名・勘違いの背景・基本の動き
ナルトダンスのBGMとして最も広く使われているのは、中国の楽曲「一笑江湖(イーシャオジャンフー)」です。歌い手は聞人聽書(闻人听書)で、作詞・作曲は祝何。2020年に配信された古風テイストの楽曲で、その後ショート動画プラットフォームでブームになった「広西科目三(广西科目三)」ダンスの定番BGMとして一気に知られるようになりました。
実際、日本のブログや歌詞サイトでも「ネット上でよく聞く中国語の歌」「ナルトダンスの曲」として一笑江湖を紹介しており、猫ミームなどの動画で白い猫が“ナルトダンス風”の動きをする時に流れている曲として言及されています。
TikTokやYouTubeショートでは、原曲にドラムや低音を強調したDJ版が多用されていて、短いフレーズをループさせた編集がされやすいことも相まって、ショート動画向きの“中毒性のあるBGM”として定着しました。
日本で混乱を生みやすいのが、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」との関係です。ライラック自体はTVアニメ『忘却バッテリー』のオープニングテーマとして2024年に発表されたロックナンバーですが、SNS上では「ナルトダンスの振付」と「ライラック」を組み合わせた動画や、「今これダンス(今これ構文×ナルトダンス×ライラック)」といった派生ミームが登場し、結果として「ナルトダンス=ライラックの曲」という誤解が生まれやすい状況になっています。
つまり、ライラックはナルトダンスの“公式曲”ではなく、後からユーザー側が掛け合わせた二次創作的な組み合わせだと整理できます。
踊りの特徴としては、科目三ダンスに共通する動きがベースになっています。上半身をやや前に倒し、左右に小刻みにステップを踏みながら、腰と肩をリズムに合わせて揺らすのがよく見られる型です。腕は肘を曲げて後ろ寄りの位置に保ちつつ、タイミングに合わせて振ることが多く、この「前傾姿勢+腕を後ろに引いたシルエット」が、アニメで描かれる忍者の走り方やナルトの疾走シーンを連想させる大きな要因になっています。
振り付けそのものは厳密に固定されているわけではなく、足さばきや上半身の揺らし方にアレンジを加えたバリエーション動画も多数存在します。共通しているのは、「一笑江湖」のビートに合わせて、体重移動と腕の振りでリズムを分かりやすく見せること。こうした“真似しやすさ”と“シルエット映え”の両立が、ナルトダンスの拡散力を支えていると言えます。
公式アニメとの違いと注意点
ナルトダンスという名前から、アニメの特定シーンやオープニングを再現した振り付けだと思われることがあります。しかし、実際には『NARUTO』の本編や公式映像に、このダンスと一致する動きは存在しません。特に誤解されやすいのが、OP「シルエット」(KANA-BOON)の疾走シーンです。キャラクターが前傾姿勢で駆け抜ける描写が印象的なため、科目三ダンスの上体の傾きや腕の位置が似て見えるだけで、直接の関連性はありません。あくまで“視覚上の連想”が生まれているに過ぎない点が重要です。
また、忍者走り(腕を後ろに伸ばして走るスタイル)との結びつきもよく話題になりますが、科目三はステップ主体のダンスであり、アニメの走り方を模した動きではありません。ユーザー側が「ナルトらしさ」を感じる部分と、元の振り付けの特徴が重なった結果として名称が定着したため、公式設定とは別物として扱うのが適切です。
注意点として、ミーム系動画は編集の自由度が高く、二次創作が広がりやすい反面、無断使用や誤情報も混ざりやすい傾向があります。特にコスプレで踊る動画や、アニメの映像を背景に合成した投稿は、著作権の取り扱いに配慮が必要です。キャラクターのビジュアルやアニメ映像をそのまま転載すると権利侵害に当たる可能性があるため、個人で楽しむ範囲を超える場合は慎重に判断する必要があります。
さらに、撮影場所や周囲の迷惑にも気を配ることが大切です。屋外で踊る動画を撮影する際には、人通りや交通の妨げにならないようにすること、第三者が映り込む環境では撮影許諾に注意することなど、基本的なマナーを守ることでトラブルを避けられます。
つまり、ナルトダンスは公式アニメとは無関係なミーム文化に由来しつつも、『NARUTO』が持つビジュアルイメージによって名前が浸透した現象です。楽しむ際は、あくまで二次的なネット文化としての距離感を保ちつつ、安全とマナーを意識することが求められます。
まとめ:偶然が重なって生まれたネット文化としてのナルトダンス
ナルトダンスと呼ばれている動きは、もともと『NARUTO』の公式振り付けではなく、中国・広西で流行した「科目三」ダンスと楽曲「一笑江湖」、そしてSNSでの編集文化が重なって生まれたミームです。元のダンスにナルトの要素が仕込まれていたわけではなく、前傾姿勢や腕の位置、シルエットの印象がアニメの忍者像と結びついて見えたことで、「ナルトっぽい動き」として受け取られるようになりました。
さらに、コスプレや編集動画、猫ミームなどが加わり、視聴者が面白がって「ナルトダンス」という名称を使い始めた結果、その呼び名が一人歩きして定着していきます。その途中で、楽曲も原曲の一笑江湖だけでなく、ライラックのような別の曲と組み合わされるなど、ユーザー側の創作によってバリエーションが増えていきました。
ナルトダンスは、元ネタのダンス文化、ショート動画のリミックス、アニメファンの連想が折り重なったところに生まれた現象です。だからこそ、公式作品と完全に同一視するのではなく、「NARUTOのイメージを借りて広がったネットミーム」として、背景を理解したうえで楽しむ視点が大切になります。作品そのものに興味を持ったなら、原作やアニメを改めて見返し、公式が描いたナルトの世界と、ネット発のナルトダンス文化の違いを意識して味わうと、どちらもより立体的に感じられるはずです。